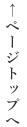コラム
-
遺品で捨ててはいけないもの14選!その理由とともに徹底解説
公開日 2024/10/10
更新日 2025/02/21
-

親族が亡くなった場合、遺品整理を行わなければなりません。何も知らずに遺品を勝手に捨ててしまうと、あとで後悔するどころか、親族同士でトラブルになるケースもあります。しかし、捨ててはいけないものが何なのかわからないという方もいるのではないでしょうか。
本記事では遺品で捨ててはいけないものを14選ご紹介します。また、捨ててはいけないものを守る方法や捨てるものの整理方法を解説します。
遺品の高価買取なら美観堂にお任せください!
買取方法・買取相場・相見積もりの依頼はこちらのバナーをクリック目次
遺品整理で捨ててはいけないもの14選
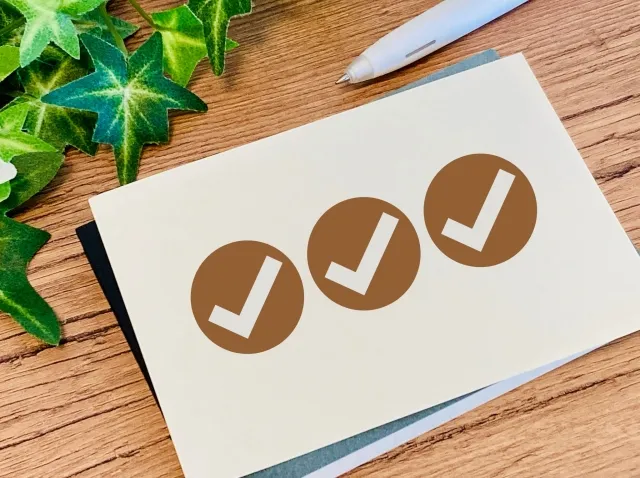
遺品整理は感情的にも大変な作業です。大切なものを見逃さないためには、どのアイテムが重要であるかを理解する必要があります。ここでは、遺品整理で捨ててはいけないものを一つずつ解説します。
遺言書・エンディングノート
遺言書は法的効力を持つ文書であり、財産分与や葬儀の希望などを明確に残す手段として活用されます。一方、エンディングノートは法的効力こそありませんが、家族に伝えたい内容を自由に書き記すことができる点が特徴です。日常生活の小さな希望や医療・介護に関する要望、保険や預貯金の情報なども整理しやすくなるため、残された遺族の負担が軽減されます。
特に遺品整理の観点では、保管場所や処分してほしくない物の指定があるとスムーズに判断を行いやすくなります。遺言書とあわせてエンディングノートを活用すると、より円滑な手続きが期待できるでしょう。
現金
遺品の中に現金が含まれている場合、捨てないようにしましょう。現金は故人の資産の一部であり、相続の対象となります。現金をへそくりとして隠しているケースもあるため、以下のような場所を探してみましょう。
- シューズBOX
- 仏壇・神棚
- 机の引き出し
- タンス・クローゼット
また、洋服のポケットに入れたままのケースもあります。遺品整理をする際は、誤って現金を捨ててしまわないよう、本のなかや洋服の間など、隅々まで探しましょう。見つかった現金は相続時に必要なため、ファイルや封筒などにまとめて保管しておきます。
通帳・カード
故人が所有していた通帳やクレジットカードは、金融資産の確認や引き出す際に欠かせないものです。故人が亡くなった事実を金融機関が認識すると口座は凍結され、現金の引き出しができなくなります。
口座凍結後に親族がお金を引き出すためには、通帳やカードが必要です。誤って通帳やカードを捨てると、親族であっても現金の引き出しが不可能になってしまうため、見つけたら大切に保管しましょう。
なお、通帳やカード以外にも、次のようなものが必要です。
- 戸籍謄本
- 遺言書
- 遺産分割協議書
銀行によって必要書類は異なるため、口座のある銀行に確認しておきましょう。
年金手帳
故人が年金を受け取っていた場合は、年金手帳も捨ててはいけません。年金受給者が亡くなった場合、死後10日(国民年金:14日)以内に「年金受給権者の死亡届」の提出が必要です。
届出が遅れ、亡くなった日以降に年金を受け取った場合、後日返金しなければなりません。
参考:日本年金機構「年金受給者が亡くなりました。何か手続きは必要ですか。」
なお、故人の方が日本年金機構にマイナンバーが収録されているケースでは、年金受給権者の死亡届は不要です。マイナンバー収録がされているかや死亡届が必要なのかが不明な場合は、早めに日本年金機構に問い合わせましょう。
身分証明書
身分証明書は、故人が契約していたサービスの解約時に必要なため、捨ててはいけません。身分証明書の種類は、以下のとおりです。
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- 保険証
- パスポート
なお、解約が必要なものには、以下が挙げられます。
- 賃貸
- サブスクリプション
- スマートフォン
- 公共料金
- インターネット
- 新聞
解約しないと料金を支払い続けてしまうため、契約していたものを確認し、一つずつ解約していきましょう。
レンタル品
レンタル品がある場合は、必ず捨てないようにしましょう。レンタル品を返却しないままにすると延滞料がかかるのはもちろん、捨ててしまうと損害賠償の対象となります。レンタル品の例は、以下のとおりです。
- WiFiルーター
- DVDやCD
- ウォーターサーバー
- リースの車
レンタル品が見つかった場合は、速やかに返却しましょう。
鍵
遺品整理をしているなかで、鍵があった場合は取っておきましょう。鍵を使用する倉庫や金庫、引き出しなどには、大切なものが入っている可能性があります。家のなかをくまなく探すのはもちろん、ポケットのなかも入念にチェックしましょう。
支払い通知書
故人の支払い通知書が見つかった場合、捨てないようにしましょう。支払通知書には、公共料金やローンなどがあります。通知書があれば、どこから現金が引き落とされているのかを確認できます。また、通知書に記載されているお客様番号から契約状況も確認できるため便利です。
故人のローンや借金などが発覚する場合もあるため、見つけた場合は捨てずに保管しておきましょう。
骨董品・美術品
骨董品・美術品が出てきた場合も、捨てないようにしましょう。価値のあるものは、売却により利益を得ることが可能です。利益は相続の対象となるため、捨ててしまうとほかの相続の方とトラブルになってしまう恐れがあります。
価値のある骨董品や美術品には、以下のようなものが挙げられます。
- 絵画や掛け軸
- 着物
- 焼き物や陶磁器
価値がありそうだと思ったものは、買取専門店で買い取ってもらいましょう。専門的な知識のあるプロに依頼すれば、高値での売却が期待できます。
関連記事:遺品整理で買取できる遺品が出てきたら?買取先を解説
貴金属
貴金属も価値のある遺品の一つであるため、捨ててはいけません。貴金属も買取店やフリマサイトなどで売却すれば売却価格が手に入ります。また、貴金属も相続の対象となります。貴金属の例は、以下のとおりです。
- 宝石
- 指輪やネックレスなどのアクセサリー
- 板金
関連記事:遺品整理で高額買い取りが期待できるものとは?高く売るためのコツも紹介
写真
故人の写真は、捨てずにとっておきましょう。写真を捨ててしまい、あとになって後悔してしまう方も少なくありません。ただ、写真だと大量で保管が難しいケースもあるため、その場合は、USBやDVD、クラウドサービスを利用するのがおすすめです。
自分でデータを残す場合は、家にあるコピー機のスキャナーが利用できます。また、コンビニのコピー機でもスキャナーが可能です。大量の写真をスキャナーでデータ化するのが面倒な方は、カメラ屋に依頼すると良いでしょう。
個人宛の手紙
手紙やはがきも取っておきます。亡くなったことを知らせる際、手紙やはがきの住所が役立ちます。また、故人との交友関係を知るためにも便利です。
葬式やお通夜などに参加できておらず、故人とお別れできていない方がいる場合は、早めに訃報の連絡をしましょう。
仕事に関する資料
仕事に関する資料が出てきた場合、捨てずに保管しておきましょう。働いていた会社で引き継ぎの際に必要になる場合があるからです。仕事の資料が出てきたら、自分たちで処分するかを判断せず、会社に確認してみましょう。
デジタル遺品
デジタル遺品とは、スマートフォンやパソコン上にあるデータのことです。写真や動画などのデータ以外にも、暗号資産や有価証券など、資産になるものも含まれている可能性があります。
スマートフォンやパソコンは資産になるものの把握や契約の解除が済むまで、保管しておきましょう。また、初期化するのも厳禁です。
残すべき遺品なのか迷った場合の対処法
捨てていいものか判断に迷う遺品は、法的・金銭的価値や思い出の深さによって扱いが異なるため、すぐに処分しないことが大切です。複数の視点で確認することで、残すべき大切な遺品を誤って廃棄してしまうリスクを減らせます。家族や専門家の意見を取り入れつつ、残すかどうかを総合的に判断する習慣が重要です。
思い出の品と実用品で区別する
まずは、故人との思い出や感情的な価値が強い遺品と、今後も使用可能な実用品を分けます。思い出の品は写真や手紙など形見として保管されることも多く、実用品は日常生活で再利用できるかどうかで判断します。こうした区別によって、感情面と実用面を整理しやすくなるでしょう。
法的価値や金銭的価値があるものを区別する
土地や家屋の権利書、金融関連書類、証券類、骨董品など、法的あるいは金銭的価値を持つ遺品は慎重な取り扱いが求められます。相続手続きや財産分与に影響する可能性があるため、早々に破棄するのではなく、相続人全員の同意や専門家への確認を行ってから処分の可否を検討してください。
処分の判断を慎重にするべき品を区別する
思いがけず高価値を有する美術品や古書類、音楽や写真データが収録されたメディアなど、存在意義を見逃しがちな品もあります。故人が大切に保管していた背景を考慮しながら、本人が意図していた使い道や想いを再確認すると、不要だと思い込んでいた物の重要性に気付く場合もあります。
大切な遺品を捨てないための対処法
遺品の整理を急ぐあまり、大切な物まで廃棄してしまうケースは少なくありません。処分前に情報をきちんと洗い出し、家族や関係者と共有することが不可欠です。特に法的効力を持つ遺言書や重要書類、個人の思い出が詰まった品などは、あらかじめ優先して確認する仕組みを整えておくと安心です。
遺言書やエンディングノートを最初に確認する
遺品を整理する前に、まず遺言書とエンディングノートがあるかどうかを調べます。遺言書は相続や遺産分割に直接関係し、エンディングノートには処分してほしくない品や保管場所が明記されている場合があります。
これらを確認することで、大切な遺品を誤って捨てずに済む可能性が高まります。捨ててはいけないものをリストアップする
整理の初期段階で「絶対に処分を避けたい物」を洗い出し、リスト化しておくと誤廃棄のリスクを減らせます。リストには重要書類や金銭的価値の高い品、思い出深い品などを漏れなく含めましょう。家族全員で共有しておけば、共同作業の際にも混乱が少なくなります。
遺品整理の際に捨ててはいけないものを守る方法

遺品整理の際、誤って大切なものを捨てないようにするには、どうしたら良いのでしょうか。ここでは、大切な遺品を守る方法を解説します。
生前に親族で話し合っておく
遺品整理で大切なものを捨てないよう、生前に親族で取っておく遺品について話し合っておきましょう。あらかじめ遺品について話し合っておけば、親族同士のトラブルを避けられます。また、本人に確認しておけば大切な遺品が明確化するため、スムーズに整理が進められます。
遺書に従う
遺書があれば、その指示に従いましょう。遺書には、遺品の処理方法に関する具体的な指示が記載されている場合があり、その内容には法的な拘束力があります。そのため、親族は遺書に従って遺品整理をしなければなりません。
勝手に判断して捨てると親族間でトラブルに発展する場合もあります。トラブルを避けるためにも、遺書に書かれている内容に沿って遺品整理を行いましょう。
エンディングノートを確認する
エンディングノートがある場合は、こちらも確認しましょう。エンディングノートとは、自分に関する情報(財産情報や家族への思いなど)が書かれたノートのことで、遺品に対してどうしてほしいかなどが記載されている可能性があります。
遺書とは異なり法的な拘束力はありませんが、故人の遺志を尊重しつつ、遺品整理を進められます。
判断に迷う遺品は残しておく
捨ててよいかわからないものは、勝手に捨てずにとっておきましょう。適当に捨ててしまうと、あとでトラブルにつながる恐れがあります。捨てずにとっておいた遺品は、親族同士で話し合い、どうするかを決定します。
関連記事:高く売れる骨董品とは?売却で意識したい7つのコツと6つの注意点
写真はデータに残す
遺品の中でも写真は思い出として最も大切な品の一つです。ただしアルバムが大量にある場合、物理的な保管スペースが問題になることもあります。必要な写真をスキャンしてデータ化すれば、場所をとらず複数の親族で共有できるメリットが生まれます。大事な思い出を残しつつ、整理の負担を軽減する手段として検討するとよいでしょう。
捨ててはいけないもの以外の遺品の整理方法

捨ててはいけないものを複数あげてきましたが、捨てるものはどう整理していけば良いのかと疑問に思う方もいるのではないでしょうか。ここでは、捨ててはいけないもの以外の遺品整理の仕方を解説します。
売却する
捨てて良い遺品は、売却できないかを考えましょう。例えば、まだ使えそうな家電や家具、衣服、自転車などがある場合、リサイクルショップやフリマアプリなどで売却できる場合があります。
リサイクルショップの場合、価値がなかったとしても無料で処分してもらえる可能性もあります。
関連記事:遺品整理の重要性と実際に売れるものとは?買取の注意点も解説
ゴミに出す
必要のない遺品は、ゴミに出しましょう。燃えるゴミ・燃えないゴミなど、分別方法により収集する曜日は異なるため、自治体に確認したうえで、少しずつゴミを出します。粗大ごみを処分したい場合、自治体に申請したり施設に持ち込んだりして処分できます。
自治体によって粗大ごみの処分方法は異なるため、自治体に問い合わせてみましょう。
寄付する
遺品整理で不要なものが出てきたとしても、まだ使えるものや価値があるものが含まれていることがあります。寄付を受け付けている団体は、衣類や家具、家電製品、本やおもちゃなどを必要としている人々に届けてくれるため、社会貢献になるでしょう。
寄付先には、NPO団体やNGO団体などが受け入れ先として挙げられます。寄付する場合は、送料の負担が必要な場合もあるため確認しましょう。
遺品整理のときは捨ててはいけないものを把握しておこう
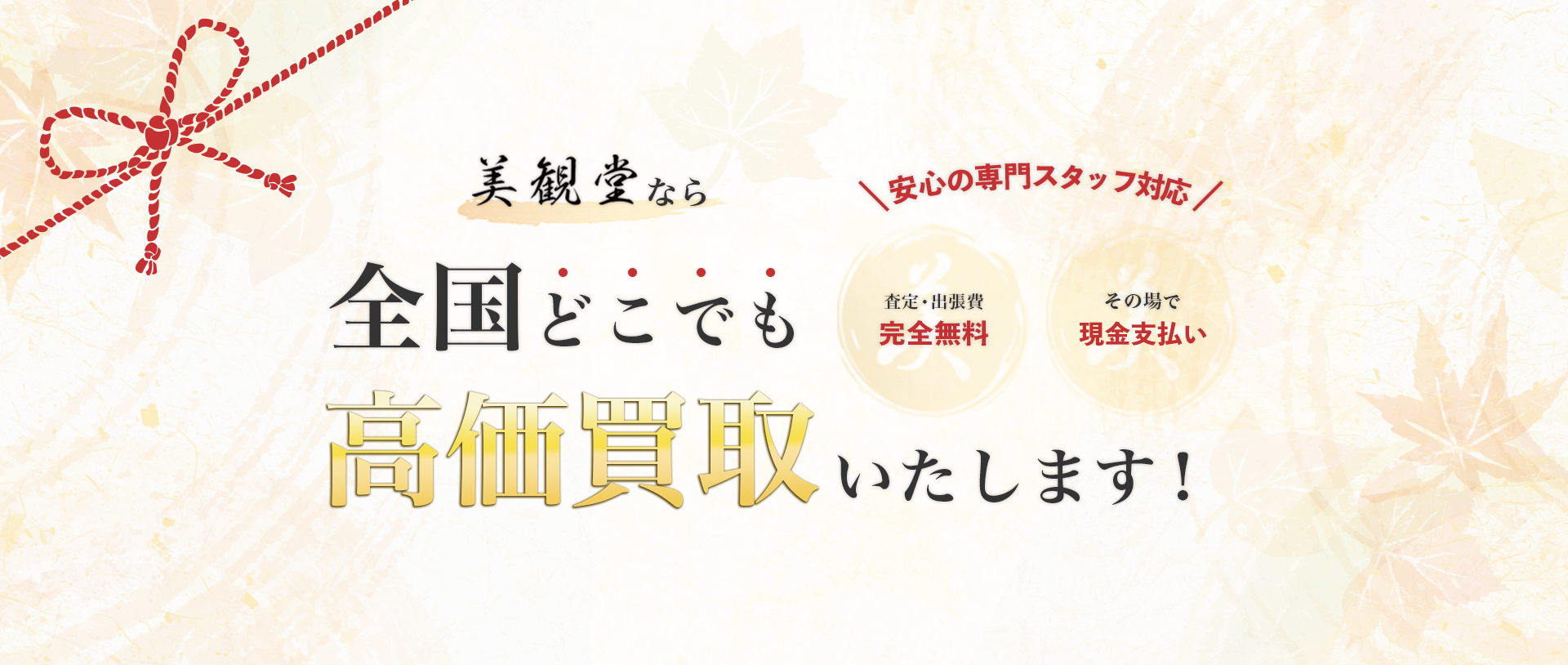
遺品整理をする際、捨ててはいけないものには身分証明書や遺言書などさまざまなものがあります。何も知らずに勝手に捨ててしまうと、のちのちトラブルに発展するケースも少なくありません。トラブルに発展させないよう、あらかじめどれを捨てるか・捨てないかを親族同士で話し合っておくことが大切です。
遺品整理を進める中で、陶器や絵画などの骨董品が見つかることがあります。遺品の買取なら美観堂にお任せください!
遺品整理の際に見つかった骨董品の買取を行っております。買取実績が豊富なうえ、査定のプロが丁寧に査定を行うため安心して取引が行えます。気になる方は、ぜひお気軽にご相談ください。この記事の監修者

義村 安悟(よしむら あんご)
《経歴》
美観堂 大阪本店店長 査定歴15年
《コメント》
複数の店舗で店長としての経験を活かし、身の回りのさまざまなジャンルのお品物を丁寧に査定しています。特に古美術品の買取においては、作品の歴史や芸術的価値、作家や時代の背景を考慮して査定を行っており、状態だけでなく市場の動向を踏まえ、公正で適正な価格設定を心がけております。
また、遠方にお住まいのお客様からのご依頼も多い中、出張買取を通じて、さらにお役に立てるよう努めてまいりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。《許可証》
古物商営業許可番号:第62111R051143号
美観堂買取
〒542-0062大阪府大阪市中央区
上本町西5丁目3-3ワンダー5ビル1F
選ばれる理由
|
|
|
|


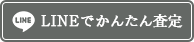
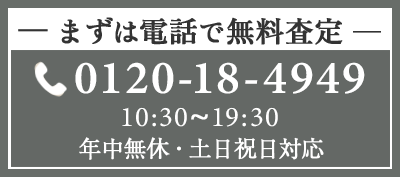





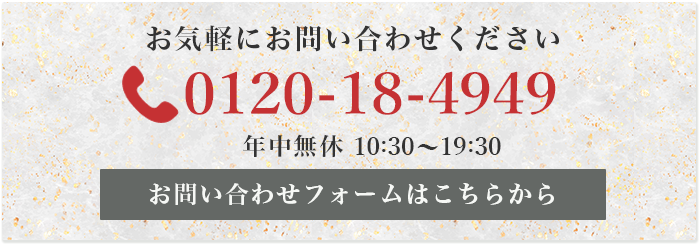



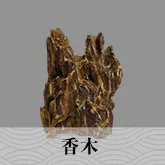
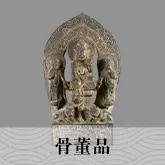


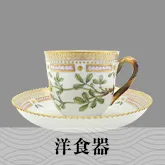
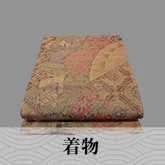
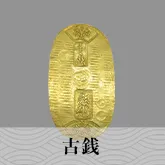



 査定・出張費無料
査定・出張費無料 キャンセル無料
キャンセル無料 安心・信頼
安心・信頼 丁寧・迅速
丁寧・迅速