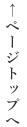コラム
-
高く売るコツ骨董品について
古銭を洗浄すると価値が下がるのか?正しい洗浄方法も紹介
公開日 2025/04/18
更新日 2025/04/30
-

古銭の洗浄は、場合によっては価値を下げてしまうリスクがあります。しかし、正しい方法で行えば、汚れを落として保存状態を向上させることにつながります。
本記事では、洗浄が適しているケースや素材別の具体的な方法、注意点や保管方法までを詳しく解説します。古銭の保管や管理で悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
古銭の高価買取なら美観堂にお任せください!
買取方法・買取相場・相見積もりの依頼はこちらのバナーをクリック目次
古銭は洗浄してもいい?

古銭を洗っても良いのかどうかは、コレクターにとって非常に悩ましいテーマです。というのも、洗浄によって硬貨の外観が改善することもある一方で、価値が損なわれることもあるためです。
硬貨は長年の使用や保存環境によって汚れやサビが付着しますが、それが「歴史の証」として評価されることもあります。とはいえ、すべての古銭が「洗ってはいけない」とは限りません。状態や目的によっては、正しく洗浄することで保存性が向上し、美観が保たれることもあります。
ここでは、洗浄によって価値が変動するケースや、注意すべきポイントについて詳しく見ていきましょう。
価値が上がるケース
古銭の中には、長い年月によって厚く汚れが付着し、本来の姿が見えにくくなっているものもあります。このような状態であれば、洗浄によって表面の汚れが除去されることで、銭文や刻印が判別しやすくなる可能性があります。
鑑定の際、文字や模様がしっかりと確認できる状態であることは、正確な評価を受けるために有利に作用します。また、軽度の汚れを落とすことで保存状態が改善され、今後の劣化防止にもつながるでしょう。
関連記事:古銭のおもな処分方法と高値買取を実現するために意識したいポイント
価値が下がるケース
一方で、古銭を洗浄すると本来の価値を著しく損なうおそれがあります。具体的には、磨き過ぎや研磨により、表面に細かな傷がついてしまうケースです。
古銭の価値は「当時の状態をどれだけ保っているか」によって左右されるため、人の手による後加工が見受けられると、それだけで評価が下がる要因となることがあります。無理に輝かせようとして研磨剤を使用する、金属ブラシで擦るなどの行為は、本来の風合いや経年の味わいが損なわれ、買取価格に悪影響を及ぼす可能性があります。
たとえ汚れていても、自然なままの状態が評価されるケースもあるのです。
法令違反を問われるケース
古銭や硬貨の洗浄に関して、もう一つ重要な視点が「法律」です。日本には「貨幣損傷等取締法」の法律があり、意図的に貨幣を変形させたり傷つけたりする行為が禁止されています。
硬貨を強く擦って刻印が消えてしまう、曲げたり穴を開ける、といった行為は法律に抵触する可能性があるでしょう。違反した場合は懲役や罰金が科されることもあるため、たとえ古銭であっても慎重に扱う必要があります。
古銭は文化財や歴史的資料としての価値もあるため、取り扱いには十分な配慮が求められます。
古銭の正しい洗浄方法

古銭を洗浄するときは、素材に応じた方法を選びましょう。見た目は似ていても、金、銀、銅、アルミニウム、ニッケルなど、素材によって反応の仕方や傷の付きやすさが大きく異なるためです。
ここでは、金貨・銀貨・銅貨といった金属ごとの洗浄方法に加え、紙幣の扱いについても触れていきますので、正しいケアのための参考にしてください。
金貨
金貨は非常に柔らかい金属でできており、軽い摩擦でも表面に傷がついてしまう繊細な性質です。そのため、汚れが気になる場合でも、強く擦ったり研磨剤を使うのは避けるべきです。
基本的には、柔らかい眼鏡拭きのような布で軽く撫でるように拭くのが最も安全な方法です。
また、重曹を溶かしたぬるま湯に数分間漬けておくと、表面の軽い汚れが浮きやすくなり、その後、やさしく水洗いし拭き取ることで、金貨の質感を保ったまま清潔な状態にできます。
銀貨
銀貨は時間の経過とともに表面が黒ずみやすい素材ですが、これは空気中の硫黄分との化学反応によるものであり、銀に特有の経年変化とされています。そのため、洗浄の際は化学反応を利用した方法が効果的です。
重曹とアルミホイルを組み合わせた方法は、酸化銀を還元して銀本来の輝きを取り戻す手段としてよく知られています。歯磨き粉や研磨剤入りクリーム、専用の貴金属クロスを使用する方法も挙げられます。
ただし、力加減に注意が必要で、力を入れすぎると銀貨の表面を削ってしまうため、あくまでも軽く撫でる程度に留めるのがポイントです。
銅貨
銅貨は汚れが付きやすい反面、比較的扱いやすい素材であるため、家庭にある身近なもので洗浄できるのが特徴です。酢やレモン汁などの酸性調味料に数分浸してからやさしく拭き取ると、表面にこびりついた酸化汚れがスッと落ちることがあります。
また、ペースト状にして塗布し、その後に軽く擦る方法も効果的とされています。さらに、重曹を混ぜた水で磨くことで、黒ずみやサビも比較的簡単に落とせるでしょう。
いずれの方法であっても、最後に水で丁寧に洗い流し、水分を十分に拭き取ることが重要です。
アルミニウム素材の古銭
アルミニウムは非常に軽く柔らかい金属であり、酸に対しても反応しやすいため、洗浄方法には特に気をつけてください。酸性の酢やクエン酸を使用すると表面が曇る、あるいは腐食するおそれがあるため、使用は避ける必要があります。
アルミ硬貨は中性の洗剤をほんの少量使い、指先や柔らかいクロスで優しく拭くのが安全です。汚れがひどい場合は、重曹をペースト状にして塗り、そっと撫でるように磨いた後、水で洗い流して乾かしましょう。
ニッケル素材の古銭
ニッケルを含む硬貨は硬度が高く、耐久性に優れた素材ですが、過剰な摩擦や化学的処理に注意が必要です。基本的には重曹を水に溶かしてペースト状にし、指や柔らかい歯ブラシでやさしく擦る方法がおすすめ。
また、クレンザーなどに含まれる研磨成分を利用して洗浄する方法もありますが、その場合は磨きすぎないよう加減しましょう。ニッケルは水に強いため、洗浄後はしっかり水洗いし、水分を残さず拭き取って保管するのがポイントです。
見た目以上に傷つきやすい金属であることを念頭に、慎重に扱いましょう。
お札
紙幣は基本的に洗浄してはいけません。紙の素材そのものが水や摩擦に弱く、洗浄を試みることで破れたりシワが増えたりして、かえって状態を悪化させてしまいます。
多少の汚れや変色があっても、年代物の紙幣であればむしろ「歴史的価値」として受けられるため、無理に綺麗にしようとする必要はありません。
どうしても見た目を整えたい場合は、湿らせた状態で低温のアイロンを軽く当てる程度に留める必要があります。それでも破損のリスクは残るため、最も安全なのは、汚れていたとしても現状のまま保管し、鑑定を受けることとされています。
古銭を洗浄する際の注意点

古銭の洗浄では、単に汚れを落とせばよいというものではありません。むしろ、扱い方を誤れば、わずかな手入れであっても、価値を大きく損なうおそれがあります。
素材に合わない薬剤を使う、強い力で擦るなどの行為は、コインの表面に微細な傷がつき、それが原因で査定価格が下がるケースがあるのです。また、乾燥が不十分だった場合に、見えにくい部分でサビが進行するおそれがあるため、仕上げまで丁寧に扱う必要があります。
ここでは、古銭を安全に洗浄するためのポイントとして、道具の選び方や磨く際のコツ、乾かし方まで詳しくご紹介します。
道具の選び方
古銭を洗浄する最初のステップは、使用する道具の選定です。選ぶ道具次第で、洗浄後の仕上がりや硬貨へのダメージが大きく変わるため、素材に応じた道具を用意しましょう。
例えば、金や銀といった柔らかい素材には、研磨成分を含まないクロスや、柔らかい布を使用することが基本です。銅など比較的硬めの素材は、重曹やクエン酸を使った簡単なペーストを組み合わせると、汚れが落ちやすくなります。
ただし、塩素系の漂白剤や強い酸性液体は、コインを変色させるリスクがあるため使用は避けましょう。洗浄力よりも、硬貨を保護する視点で道具を選定することが重要です。
磨き方
磨きの工程では、とにかく「力を入れすぎない」ことが鉄則。洗浄と聞くと、ピカピカにしたいという気持ちから、つい強くこすりたくなってしまうかもしれませんが、表面を削ってしまえば、もはや本来の古銭とはみなされなくなります。
特に希少な古銭や発行当時の刻印が残っているものにとっては、わずかな擦れも大きなマイナスポイントとなります。布やブラシを使う場合は、毛先の柔らかいものを選び、円を描くように軽くなでる程度で充分です。
コイン表面に汚れが残っていても、それが歴史的な価値の一部とされることもあるため、無理に取り除こうとせず、自然な風合いを維持することが望まれます。
乾かし方
洗浄が終わったあとの乾燥も、古銭の保存状態を大きく左右します。水分が残ったまま保管すると、空気中の成分と反応して酸化が進み、数週間で再び変色が進行する可能性があります。
洗浄後はすぐに乾いた清潔な布で水気を拭き取り、必要に応じて風通しのよい場所で自然乾燥させましょう。ただし、ドライヤーの熱風などを使うと、金属の膨張・収縮によってコインが変形するリスクもあるため、使う際は温風ではなく送風にするか、短時間で切り上げてください。
完全に乾燥させた後で保存することにより、次回まで美しい状態を維持できます。
洗浄後の古銭の保管方法

古銭の洗浄が終わったあとは、きれいな状態を維持するためには、適切な保管環境を整える必要があります。空気や湿気、紫外線といった外部の影響は、金属に少しずつダメージを与え、時間をかけて変色やサビを引き起こしてしまいます。
また、手指に含まれる皮脂や汗も古銭にとっては大敵。せっかく洗浄したのに、保管方法を間違えてしまえば短期間で再び劣化するだけでなく、さらに状態が悪化する可能性もあります。
ここでは、古銭の美観と価値を損なわずに保管するための、具体的な方法について見ていきましょう。
専用ケースの利用
古銭は、空気や湿気から守るためにコイン専用ケースに収納することが望まれます。密閉性の高いケースであれば、酸化を防ぎ、硬貨表面の状態を長期間維持できます。
ケースは透明なプラスチック製、スクリュー式のものなどさまざまなタイプがありますが、重要なのは硬貨のサイズに合ったものを選ぶこと。サイズが合わないと、保管中に内部で動くことで摩擦が生じ、傷が付くおそれがあります。
自宅にケースがない場合でも、布を敷いた小箱に入れて保管するなど、できるだけ空気と接触しない工夫をすれば劣化を抑制できる可能性があります。
手袋の着用
古銭に直接手を触れるのは、保管中の劣化を早める原因のひとつです。人間の手には常に汗や皮脂が分泌されており、金属に付着すると酸化反応を引き起こし、時間とともにサビや変色を招きます。
こうしたトラブルを防ぐためにも、古銭を取り扱う際は布製やゴム製の手袋を着用するのが基本。とくに銅や銀などは指紋が付きやすく、一度触れてしまうと拭き取っても跡が残ってしまうこともあります。
コレクションや鑑賞の際も、手袋を着用して静かに取り扱うことで、美しい状態を長期間維持できます。
柔らかい布で手入れする
保管中の古銭には、目に見えない埃や汚れが少しずつ蓄積していきます。放置すると、金属の表面に染み込んでしまい、あとから落とすのが難しくなります。
そのため、定期的に柔らかい布で優しく表面を拭くお手入れがおすすめ。布は必ず乾いたものを選び、毛羽立ちの少ない眼鏡用クロスやジュエリー用の専用布を使うと良いでしょう。
洗剤や研磨剤は不要で、あくまでも軽く拭き取る程度が適切とされています。強く擦ったり繊維の粗い布を使うと、せっかくの古銭に細かな傷を付けてしまうため注意してください。
直射日光や湿気を避ける
古銭の大敵である直射日光と湿気を避けるには、保管場所の選定が非常に重要です。太陽光に含まれる紫外線は、金属に化学反応を起こし、わずか数ヶ月で表面の色合いが変化してしまうのです。
また、湿気の多い場所に置くと、素材によっては酸化が急速に進み、元の輝きを失ってしまうケースもあります。古銭を保管する際は、日の当たらない暗所で、温度と湿度の変化が少ない安定した環境を選びましょう。
必要に応じて、乾燥剤を入れた保管ボックスや防湿ケースなどを併用すると、より安全に長期保存が可能となります。
古銭の洗浄と保管は正しい方法で
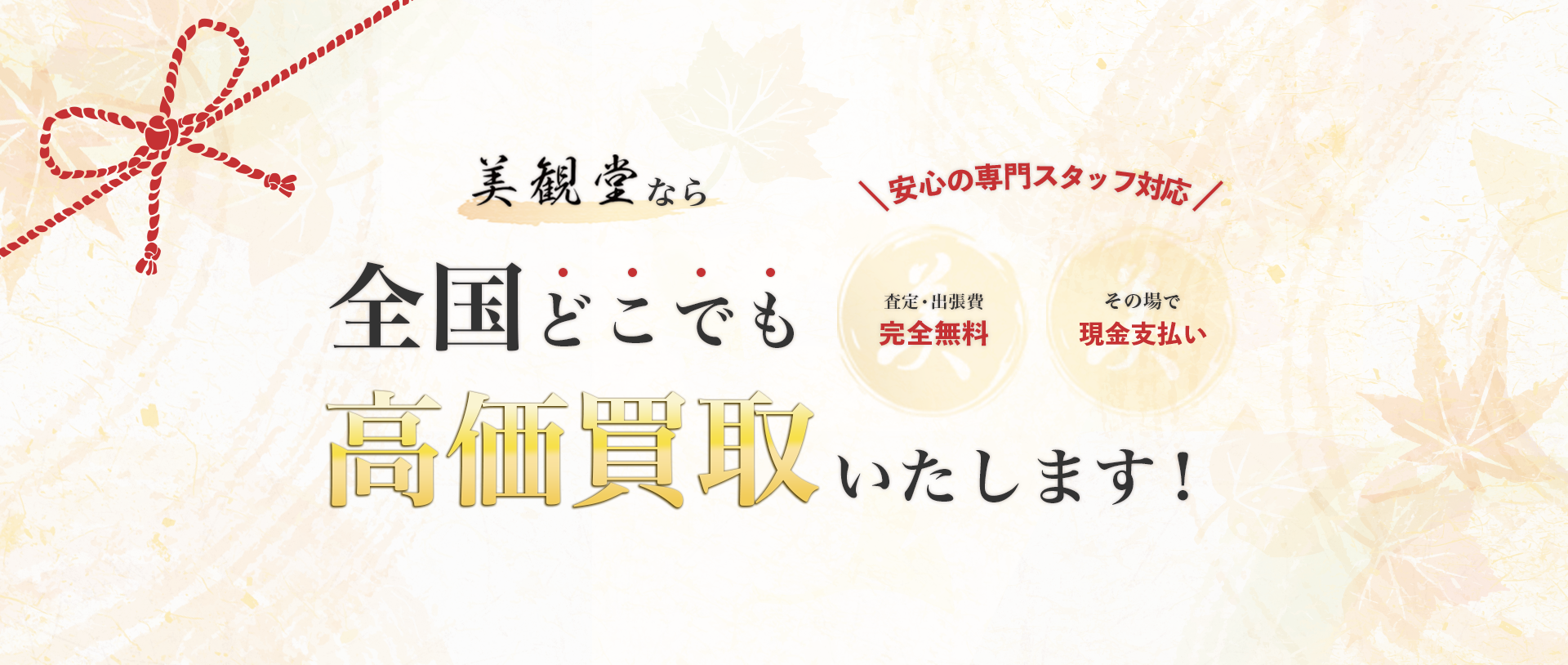
古銭の洗浄は、方法を誤ると価値を下げてしまう一方で、適切な手順を踏めば美観や保存性を高められます。素材に応じた扱い方を理解し、慎重に手入れすることが何より大切です。
古銭やお札の買取をご希望の方は、古銭の買取なら美観堂にお任せください。
信頼と実績のある専門の買取スタッフが高価査定を致します。この記事の監修者

義村 安悟(よしむら あんご)
《経歴》
美観堂 大阪本店店長 査定歴15年
《コメント》
複数の店舗で店長としての経験を活かし、身の回りのさまざまなジャンルのお品物を丁寧に査定しています。特に古美術品の買取においては、作品の歴史や芸術的価値、作家や時代の背景を考慮して査定を行っており、状態だけでなく市場の動向を踏まえ、公正で適正な価格設定を心がけております。
また、遠方にお住まいのお客様からのご依頼も多い中、出張買取を通じて、さらにお役に立てるよう努めてまいりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。《許可証》
古物商営業許可番号:第62111R051143号
美観堂買取
〒542-0062大阪府大阪市中央区
上本町西5丁目3-3ワンダー5ビル1F
選ばれる理由
|
|
|
|


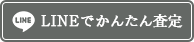
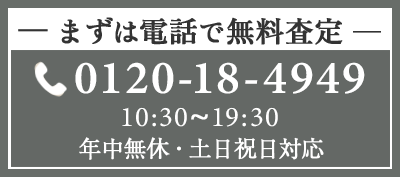





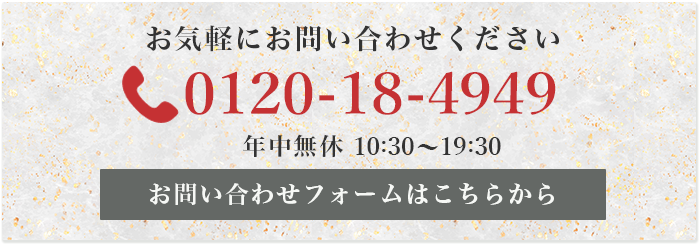



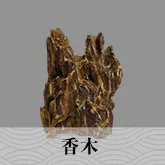
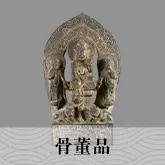


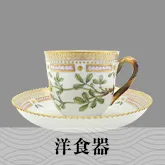
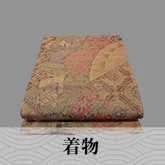
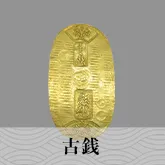



 査定・出張費無料
査定・出張費無料 キャンセル無料
キャンセル無料 安心・信頼
安心・信頼 丁寧・迅速
丁寧・迅速