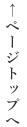コラム
-
骨董品について
寛永通宝とは?歴史・種類・価値などを解説
公開日 2025/04/21
更新日 2025/04/30
-

寛永通宝は江戸時代から明治初期にかけて流通した代表的な銭貨で、現在も収集家の間で高い人気を誇る古銭とされています。
この記事では、寛永通宝の語源や特徴、歴史的背景について解説しています。「古寛永」と「新寛永」の違い、さらに各種類ごとの価値や買取価格についても紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
古銭の高価買取なら美観堂にお任せください!
買取方法・買取相場・相見積もりの依頼はこちらのバナーをクリック目次
寛永通宝とは?

寛永通宝は、江戸時代に初めて鋳造された銅貨で、日本における長い貨幣の空白期間を経て登場した歴史的な通貨です。流通の開始は寛永年間にさかのぼり、その後の日本社会に深く根づく存在となりました。
通貨としての機能に加え、経済や政治の動向とも密接に関わり、当時の庶民生活にも深く関与していたとされています。まずは、「寛永通宝」という名前の由来や、鋳造過程で使われる母銭と流通用の通用銭の違いについて見ていきましょう。
語源
「寛永通宝」の名称は、発行が始まった元号である「寛永」に由来しています。元号の一文字と、通貨としての性質を表す「通宝」を組み合わせ、中国の銭貨制度の影響を受けた命名法に基づいたものとされています。
江戸幕府が安定した財政と統一的な貨幣制度を築こうとした象徴として、この名称が採用されたと考えられています。また、この時代の貨幣にしばしば見られるように、名称に政治的安定や国家の繁栄を願う意味も込められていました。
母銭と通用銭との違い
寛永通宝には、実際に人々の手に渡って使われた「通用銭」と、鋳造するための基となる「母銭」という2つの種類が存在します。
通用銭は日々の買い物や取引に使われた一般的な銭貨で、大量生産が前提とされていました。そのため、鋳造の効率を高めるために、金属を流し込む鋳型が必要になります。この鋳型を作る元となる精密な見本が母銭です。
母銭は職人の手で丁寧に仕上げられ、通用銭に比べ精巧な造りをしていますが、基本的には市場で使用されることはありませんでした。かつては価値がないとみなされていた母銭も、現在ではその希少性から高い評価を受けています。
寛永通宝の歴史

寛永通宝は、江戸幕府によって制度化された銅貨であり、貨幣としての役割だけでなく、幕府の財政運営や庶民経済の安定に大きく貢献した存在です。登場から終焉に至るまで、数世代にわたって日本人の生活と密接に関わってきました。
ここでは、幕府の公式貨幣として発行された背景と、明治維新以降の取り扱いについて詳しく見ていきましょう。
江戸幕府の公式貨幣
寛永通宝が公式に登場したのは、1636年、第三代将軍・徳川家光の治世でした。それまで日本では質の異なるさまざまな私鋳銭が混在し、貨幣制度の混乱が続いていました。
こうした背景を踏まえ、幕府は金・銀・銭の三貨制度を整備し、銅貨の基盤として寛永通宝の発行に踏み切ります。この貨幣は、庶民の小額取引に広く用いられ、特に流通量の多さと鋳造の継続性において、歴史的に極めて重要な位置にあったと考えられています。
素材や鋳造地によって多様なバリエーションが存在し、それぞれが幕府の統制と地域の経済を映し出す鏡のような役割を果たしていたといえます。
明治時代以降の取り扱い
明治維新によって江戸幕府が幕を閉じると、日本は新たな貨幣制度への転換期を迎えることになります。1871年に制定された新貨条例では、「円・銭・厘」を基本とする新たな通貨体系が導入され、寛永通宝は一厘相当の補助貨幣として暫定的に存続します。
その後、1873年に正式に法定通貨ではなくなりますが、特定の種類はしばらく流通が一部で継続して認められていました。最終的に、1953年にすべての旧銭が廃止され、寛永通宝も公式な役目を終えることになります。
300年以上の時を経て人々の手元を行き交ったこの銭貨は、今では歴史資料として、高い評価を受けており、収集対象として根強い関心を集めています。
関連記事:富本銭・和同開珎の違いと富本銭が最古の貨幣と考えられている理由
寛永通宝の「古寛永」と「新寛永」の違い

寛永通宝は、長い鋳造期間の中で「古寛永」と「新寛永」の時代区分が生まれました。
古寛永とは
最初期にあたる古寛永は、寛永年間から万治年間にかけて各地で鋳造されたもので、幕府の管理が比較的緩やかだったことから、地域ごとに異なる書体や仕上がりが見られます。
銭の大きさや厚み、刻まれた文字の形状もまちまちで、職人の技術や素材の違いによる品質のばらつきが特徴です。
新寛永とは
一方で、新寛永は幕府が鋳造体制を再整備した後に発行されたもので、江戸の鋳造所などで中央集権的に管理された結果、品質が飛躍的に向上しました。
銭のサイズや重量、文字の整い方に統一感があり、見た目にも鋳造精度の高さが明確に認識できる仕上がりとなっています。
寛永通宝「古寛永」の代表的な種類と価値(買取価格)
.webp)
寛永通宝の中でも、初期に鋳造された「古寛永」は、種類ごとに書体や形状に個性があり、それぞれに異なる魅力と価値があります。江戸幕府の方針により各地の大名や藩が鋳造を担ったことで、地域色豊かな寛永通宝が多数誕生しました。
以下の表では、古寛永の中でも代表的とされる種類と、おおよその買取相場をまとめています。
種類名 買取価格の目安 二水永 1,000円~50,000円 芝銭 数十円~500円 浅草銭 500円~1,000円 坂本銭 数百円~1,000円 水戸銭 100円~500円 松本銭 5,000円~10,000円 吉田銭 数百円前後 高田銭 数百円前後 仙台銭 数百円~1,000円程度 岡山銭 数百円~数千円程度 長門銭 数百円~数千円程度 建仁寺銭 数百円~数千円程度 沓谷銭 数百円前後 鳥越銭 数百円前後 初心者には見分けが難しいものも少なくありません。鑑定や査定を受けることで、意外な高額査定につながるケースもあるでしょう。
ここからは、種類ごとの特徴や市場価値について解説していきます。
二水永
二水永は、寛永通宝の初期に鋳造された非常に珍しい銭貨で、寛永3年に常陸国水戸の商人・佐藤新助によって発行されました。その名のとおり、「永」の字が「二」と「水」を合わせたような独特の書体で刻まれており、他の寛永通宝とは明確に区別できます。
また、裏面には「三」や「十三」といった刻印があるものが知られており、発行年を示すものと考えられています。幕府および水戸藩の許可を得て鋳造されたものの、私的な発行だったことや、鋳造数が限られていたことから、現存数は極めて少ないとされています。
状態の良い美品であれば数万円以上で取引されることもあり、現在では、希少性の高さからコレクターの注目を集めており、市場でも高く評価されています。
芝銭
芝銭は、寛永13年に江戸の芝で鋳造された初期寛永通宝のひとつ。幕府が本格的に銭貨制度を開始した際の、重要な銭座から生まれました。
特徴としては、「通」の字が草書体風に崩れている「草点通」と呼ばれる書体で刻まれている点が挙げられます。また、「永」の字にも独自の表現が見られ、全体的に素朴ながら力強い印象を受ける仕上がりになっています。
芝銭は比較的鋳造数が多く現存数も多いため、希少性には乏しいものの、江戸初期の貨幣制度を知る資料として評価されています。市場価格は状状態によって価格に差があり、数十円から500円程度で取引される例も見られますが、「母銭」であれば、数千円から高値で取引されることもあります。
浅草銭
浅草銭は、寛永13年に江戸・浅草で鋳造された初期寛永通宝の一種で、「志津磨百手」といった別名で知られていることもあります。最大の特徴は、他の同時期の銭貨に比べて文字の配置が整い、全体として均整の取れた美しさを備えている点にあります。
浅草の鋳造所は幕府の厳格な管理下に置かれていたため、品質管理も徹底されており、銭文のくっきりとした仕上がりが評価されています。書体には細かなバリエーションが複数存在し、それぞれに異なる評価がなされています。
現存数が多いことから希少性はそこまで高くないものの、初期鋳造の代表格として市場では安定した人気があり、保存状態によっては500円から1,000円前後で取引されるでしょう。
坂本銭
坂本銭は、近江国坂本で寛永13年に鋳造された寛永通宝で、江戸と並ぶ幕府公認の鋳造拠点である坂本銭座において製造されました。特徴的なのは、「永」の字の右上が勢いよく跳ねているような書体で、この形状は「跳永(はねえい)」と呼ばれ、坂本銭を見分ける際の手がかりになるのです。
坂本銭は地方鋳造でありながら、江戸と並ぶ初期鋳造地であることから歴史的価値も高く、古銭収集の分野では高い注目を集めています。
ただし、発行枚数が少ないわけではなく、一定数の現存が確認されているため、買取相場は数百円から1,000円程度に落ち着いています。
水戸銭
水戸銭は、寛永14年に常陸国水戸で鋳造された寛永通宝の一種で、江戸初期における地方鋳造銭として広く知られています。見分ける際のポイントは、「永」の字の左側の縦画が特に太く強調されており、全体として力強い印象を受けることから「力永(りきえい)」と称される書体にあります。
また、初期に鋳造された「二水永」との関係性も指摘されており、水戸地域における鋳造の歴史的背景を考察する上で重要な存在とされています。
水戸銭は鋳造量が多かったため、市場での流通も比較的豊富です。そのため、価値は数百円程度が一般的ですが、稀に希少な書体や美品が高額で取引される場合もあります。
松本銭
松本銭は、寛永14年に信濃国松本で鋳造された初期の寛永通宝で、発行枚数が極めて少ないことから高い希少性をもつ銭貨です。最大の特徴は、「宝(寳)」の字の左側が右上に向かって大きく傾いている独特の書体にあり、「斜宝」あるいは「縮宝」と呼ばれています。
松本藩の今井家が鋳造を請け負った記録が残っており、今井家に伝わる枝銭(未使用の見本銭)が松本市立博物館に寄贈されたことで、その存在と背景が広く知られるようになりました。
現存数が極めて限られているため、状態の良いものには数千円から1万円近い高値が付き、コレクターの間では非常に人気の高い種類となっています。
吉田銭
吉田銭は、寛永14年に三河国吉田(現在の愛知県豊橋市)で鋳造されたとされる初期寛永通宝です。書体の主な特徴は「通」の字が草書体風に崩れた「草点通」と呼ばれる点で、「永」の字にも独自の表現が見られます。
吉田藩は徳川家康の次男・結城秀康がゆかりをもつ藩であり、吉田銭もその歴史的背景の一端を物語る存在といえるでしょう。
ただし、流通量は比較的多かったと考えられ、現在も一定数の現存が確認されています。そのため、古銭市場における価値は数百円前後にとどまり、希少性という観点ではやや控えめでしょう。
高田銭
高田銭は、寛永14年に越後国高田(現在の新潟県上越市)で鋳造された寛永通宝で、高田藩によって管理された鋳造例のひとつです。「永」の字が下部に向かって大きく広がっているような形状が特徴で、「笹手永(ささてえい)」と呼ばれる書体で知られています。
この文字の形は一目で見分けがつくため、古銭初心者でも識別しやすい種類の一つと言えるでしょう。高田藩は、家康の六男・松平忠輝が治めたことで知られ、江戸幕府とのつながりも深い土地柄でした。
現存数は比較的多く、市場価格は数百円台が中心となっていますが、保存状態が良好なものや書体に個性のあるものは高めに評価されるケースもあります。
仙台銭
仙台銭は、寛永14年に陸奥国仙台で鋳造された銭貨で、仙台藩が鋳造を許可された数少ない例の一つとして知られています。「寛永通宝」の文字が全体的にやや小ぶりで、中央にバランスよく配置されている「中字銭」と呼ばれる書体が特徴。
見た目にも整った印象を持ち、丁寧な仕上がりで高く評価されています。仙台藩は、独自の経済基盤をもっており、この仙台銭も地域経済の一環として鋳造されたと考えられています。
市場価値は数百円から千円程度が相場であり、書体のバリエーションによってはコレクターに高く評価されることもあります。
岡山銭
岡山銭は、寛永14年に備前国岡山で鋳造された初期の寛永通宝です。特徴は、「通」の字の上部と下部がわずかに離れているように見える「離頭通(りとうつう)」と呼ばれる書体が使われている点にあります。
岡山藩は池田輝政の流れを汲む池田家が治めており、幕府との結びつきも強く、重要な役割を担っていたとされています。鋳造量は比較的少なかったとされ、現存数も限られています。
そのため、岡山銭の価値は数百円程度である一方、書体や保存状態により数千円台で取引される場合も見られます。
長門銭
長門銭は、寛永14年に長門国(現在の山口県西部)で鋳造された寛永通宝で、毛利氏の拠点である長門藩が鋳造を担った銭貨です。「永」の字が上下に潰れたような独特の形で、「俯永(ふえい)」と呼ばれる書体が用いられているのが特徴です。
岡山銭にも似た書体が存在するため、識別に注意しないといけません。希少性という面では中程度で、数百円から状態によっては数千円での取引も確認されています。
書体のバリエーションや鋳造背景に関心を持つ収集家の間では、根強い人気を誇る種類とされています。
建仁寺銭
建仁寺銭は、承応2年(1653年)頃に鋳造されたとされる寛永通宝の一種で、京都市東山区の建仁寺にちなみその名がつけられました。「通」の字が他の文字より一回り大きく、全体の中で存在感を放っている点が特徴です。
この「大字(だいじ)」と呼ばれる書体が、建仁寺銭の識別ポイントとなります。ただし、実際の鋳造地には諸説あり、長崎で作られた可能性も指摘されています。
建仁寺銭は歴史的な背景とともに、見た目のインパクトからもコレクターに評価されており、保存状態や書体の違いによっては数百円から数千円で取引されることがあります。
沓谷銭
沓谷銭は、明暦2年(1656年)に駿河国沓谷(現在の静岡県焼津市付近)で鋳造された寛永通宝です。特徴は、「宝」の字の下部がほかの文字よりも長く伸びている点で、この形状は「正足宝(せいそくほう)」と呼ばれています。
沓谷での鋳造は大規模に行われたと記録されており、尾州茶屋家の記録によれば2億枚もの鋳造があったと伝えられています。そのため、現存数が多く、市場では入手しやすい古銭の一つとされています。
価格は数百円程度が中心で、状態やバリエーションによって多少の変動はありますが、希少性を重視するコレクターにとってはやや控えめな存在といえるかもしれません。
鳥越銭
鳥越銭は、明暦2年(1656年)に江戸・鳥越で鋳造された寛永通宝で、江戸市中での流通を意識して作られた地域銭のひとつです。見た目の特徴は、全体の文字がやや小さめにまとめられており、バランスよく整った配置が印象的です。
中でも、「寛永通宝」の4文字が内側にぎゅっと収められているような小型の書体が採用されており、他の鋳造地の銭貨と比較するとやや控えめな印象を与えます。
希少価値の面ではそこまで高くなく、現存数も多いため、古銭市場では数百円前後で取引されることが一般的とされています。
寛永通宝「新寛永」の代表的な種類と価値(買取価格)
.webp)
「新寛永」とは、寛文8年(1668年)以降に幕府の直轄体制のもとで鋳造された寛永通宝を指します。江戸・亀戸をはじめとする鋳造地で製造され、品質が安定したことから長期にわたって庶民の生活に浸透しました。
種類は非常に多く、書体や刻印、素材の違いによって分類され、価値も大きく異なります。ここでは新寛永の代表的な種類と、買取価格の目安を一覧でご紹介します。
種類 買取価格の目安 島屋文 100,000円~300,000円 正字文・正字背文 数十円~500円 正字入文 数百円~数千円 退点文 数百円~数千円 耳白銭 数百円 日光御用銭 数万円~数十万円 正徳期背佐銭 数百円~数千円 享保期背広佐銭 数百円~1,000円 蛇ノ目 数千円~40,000円 石ノ巻銭 数百円~数万円 小梅銭 数百円~数千円 白目小字 数千円~数万円 一ノ瀬銭 数千円~数万円 長尾寛(21波) 数万円~100,000円以上 新寛永通宝の価値は、希少性や保存状態、さらには「母銭」か否かによって大きく変動します。それぞれの特徴について見ていきましょう。
島屋文
島屋文は、寛文8年(1668年)に江戸・亀戸で鋳造されたとされる新寛永通宝の最初期の銭貨です。名称は、書体に「島屋」と呼ばれる独特の書風が採用されたことに由来しており、「通」の字の頭がカタカナの「ユ」に似た形をしているのが特徴。
島屋文には裏面に「文」の文字が刻まれたものと、何も記載のない「無背」の2種類があり、文ありの方が価値は高く評価されています。
発行量が少なく現存数も限られているため、古銭市場では希少性の高い銭として扱われ、保存状態の良い個体は数十万円の高値で取引されることも珍しくありません。
正字文・正字背文
正字文・正字背文は、新寛永通宝の中で最も広く普及した種類で、標準的な書体で「寛永通宝」と刻まれた「正字」が名称の由来となっています。正字文は主に表面の文字に注目される一方、正字背文は裏面に「文」の字や波紋が入っているのが特徴です。
江戸・亀戸を中心に大量に鋳造されたため現存数が非常に多く、古銭市場では数百円程度で取引されるのが一般的。ただし、書体に微妙な違いがあり、稀少なバリエーションや母銭であれば高く評価されることもあるでしょう。
正字入文
正字入文は、寛文8年頃から鋳造された新寛永通宝で、表面に標準書体の「正字」を使い、裏面の「文」の字が「入」のように見えることが名称の由来とされています。
この文字の特徴は細かく見なければわかりにくいため、見分けるにはある程度の知識が必要です。市場での価値は数百円から数千円程度で、状態や希少性に応じて価格は変動します。
見た目は標準的でも、マニアには人気の高いバリエーションです。
退点文
退点文は、寛文8年に鋳造されたとされる新寛永通宝で、「文」の文字の点が右にずれて配置されているのが大きな特徴です。この「点の退き」が名称の由来であり、標準の「文」と比較することで違いが明確になります。
文字全体も太めで、しっかりとした印象のある造形です。流通量はそれほど多くないため、一般的な新寛永通宝よりもやや高値がつきやすく、数百円から数千円の価格帯で取引されています。
母銭であれば高額査定も期待できるでしょう。
耳白銭
耳白銭は、正徳4年(1714年)に江戸・亀戸で鋳造されたとされる銭貨で、縁(通称:耳)が広く、白く見えることからその名がつきました。
品位の高い良質な銅が使用されたため、色味が白銅に近く、他の新寛永通宝と比べ明るく輝く印象があります。
当時の貨幣改革の一環として製造された背景もあり、品質には定評がありますが、発行数は比較的多く市場では数百円程度で取引されるのが一般的です。
日光御用銭
日光御用銭は、正徳4年(1714年)に鋳造された寛永通宝の一種で、「宝」の字の中にある「尓」にハネがない書体が特徴です。珍しい書体から、徳川将軍家が日光東照宮に参詣した際の「御用銭」として使われた可能性があるとされています。
銭自体も直径26ミリ以上と大きめで、母銭に近い作りであることも特徴。市場では非常に高い価値がつけられ、保存状態によっては数十万円規模の取引も確認されています。
正徳期背佐銭
正徳期背佐銭は、正徳4年ごろに佐渡で鋳造されたとされる銭貨で、裏面に「佐」の文字があることが特徴です。この「佐」は鋳造地である佐渡国を示しており、新寛永通宝の中では比較的珍しい地名入りの銭となります。
発行数は限られていたため、現存数も少なく、コレクターからの人気も高め。価格は状態により数百円から数千円で推移しますが、母銭や美品であれば数万円以上もなるケースもあります。
享保期背広佐銭
享保2年(1717年)に鋳造されたとされる享保期背広佐銭は、裏面に大きく明瞭な「佐」の文字が刻まれています。正徳期の背佐銭と似ていますが、「佐」の字がより大きくはっきりしている点が識別のポイント。
こちらも佐渡での鋳造とされており、地域限定の希少銭として古銭市場での注目度が高くなっています。価格帯は数百円から1,000円ほどですが、保存状態や母銭であれば高額査定となる場合もあります。
蛇ノ目
蛇ノ目銭は、元文元年(1736年)以降に京都・伏見で鋳造されたとされる銭で、縁の内側に「蛇の目傘」のような同心円模様が刻まれている点が、他の寛永通宝には見られない特徴です。
縁が太く、中央の四角穴とのバランスが美しいことから、古銭コレクターの間では非常に人気の高い種類です。
一般的な新寛永よりも明らかに目を引く見た目で、数千円から4万円程度で取引されており、母銭であれば数十万円にのぼることもあります。
石ノ巻銭
石ノ巻銭は、享保13年(1728年)に陸奥国石巻で鋳造された新寛永通宝の一種で、「重揮通背仙」と「重揮通無背」の2種が存在します。特に「通」の字に特徴的な折れがあり、「背仙」には裏面に「仙」の文字があるため、仙台藩の関与がうかがえます。
マ頭・コ頭など書体のバリエーションも多く、分類が複雑である分、コレクターの興味を惹きつける存在。価格は無背が数百円から、背仙は数万円台での取引も見られます。
小梅銭
小梅銭は、元文2年(1737年)に江戸・小梅村で鋳造されたとされる新寛永通宝で、裏面に「小」の文字が刻まれているのが最大の特徴です。この「小」は鋳造地である小梅村を示し、江戸幕府直轄の鋳銭所であった背景があります。
「広穿背小」「狭穿背小」などの細かい分類があり、文字の太さや配置によって価値が分かれます。価格帯は数百円から数千円程度ですが、状態や書体によってはコレクター価格がつくケースもあるでしょう。
白目小字
白目小字は、元文4年(1739年)に鋳造されたと考えられる新寛永通宝で、白っぽい金属色と小さな書体が特徴です。「寛」の「見」部分の跳ね方や、「白目中字」とのサイズの違いによって分類されます。
小字は希少性が高く、保存状態によっては数万円で取引される場合があります。素材や鋳造技術の違いが反映された銭として、学術的にも興味深い存在とされています。
一ノ瀬銭
一ノ瀬銭は、元文5年(1740年)以降に鋳造されたとされ、「低寛背一」と「低寛背無」の2種類が代表的です。
「寛」の字が低く構えた形をしており、裏面には「一」の文字が刻まれているものと無いものがあります。「背一」のタイプは識別しやすく、希少価値も高めに評価されやすいです。
価格は数千円から数万円におよび、母銭や美品はそれ以上の価値があるとされています。
長尾寛
長尾寛(21波)は、明和5年(1768年)に鋳造された寛永通宝で、「寛」の最後のハネが長く伸びている点が特徴です。また、裏面には21個の波紋が施されており、これが「21波」と呼ばれる理由です。
短く跳ねた「短尾寛」との違いもポイントで、波紋の数や筆運びの特徴により識別されます。希少性が高く、保存状態の良い個体や母銭であれば、数万円から10万円を超える価格で取引されるケースもあるでしょう。
寛永通宝の価値を知って売却の検討を
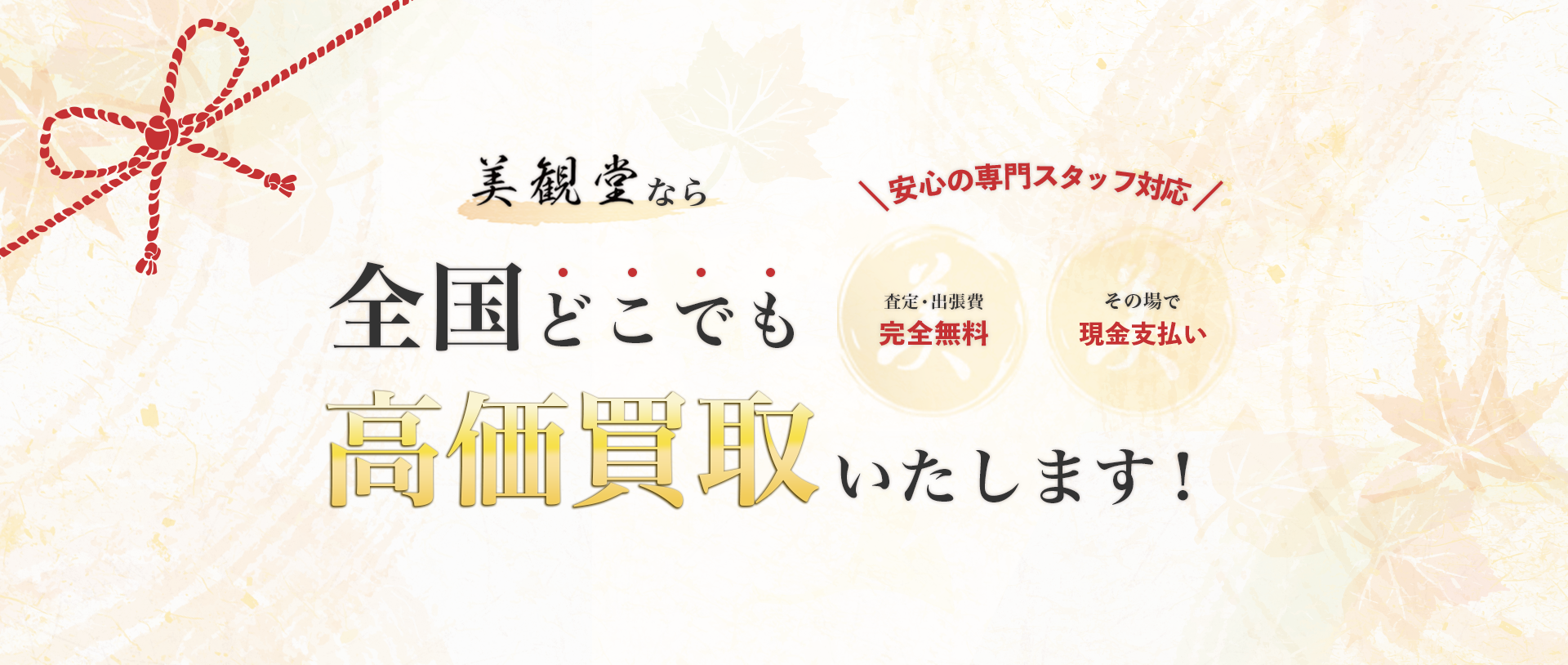
寛永通宝は、日本の貨幣史を語る上で欠かせない存在であり、「古寛永」と「新寛永」それぞれに多彩な種類と価値があります。書体や鋳造地ごとの違いを知れば、寛永通宝の魅力をいっそう実感できるはずです。
古銭の買取なら美観堂にお任せください!
寛永通宝など、古銭買取のプロが丁寧に査定させていただきます。この記事の監修者

義村 安悟(よしむら あんご)
《経歴》
美観堂 大阪本店店長 査定歴15年
《コメント》
複数の店舗で店長としての経験を活かし、身の回りのさまざまなジャンルのお品物を丁寧に査定しています。特に古美術品の買取においては、作品の歴史や芸術的価値、作家や時代の背景を考慮して査定を行っており、状態だけでなく市場の動向を踏まえ、公正で適正な価格設定を心がけております。
また、遠方にお住まいのお客様からのご依頼も多い中、出張買取を通じて、さらにお役に立てるよう努めてまいりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。《許可証》
古物商営業許可番号:第62111R051143号
美観堂買取
〒542-0062大阪府大阪市中央区
上本町西5丁目3-3ワンダー5ビル1F
選ばれる理由
|
|
|
|


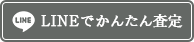
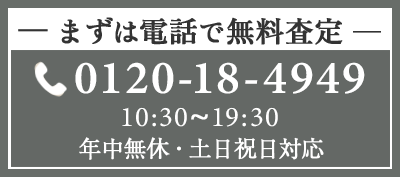





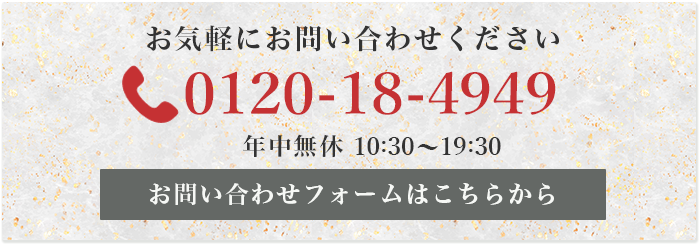



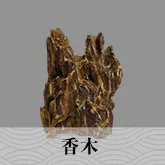
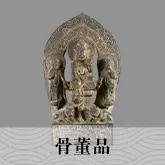


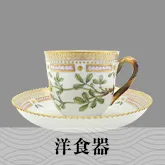
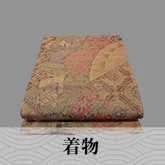
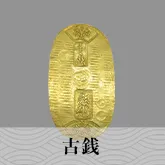



 査定・出張費無料
査定・出張費無料 キャンセル無料
キャンセル無料 安心・信頼
安心・信頼 丁寧・迅速
丁寧・迅速