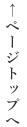コラム
-
日本刀の銘の種類・13パターンの意味と無銘の刀がある理由について
公開日 2025/04/18
更新日 2025/04/30
-

刀の買取を希望されている方に向けて、銘について解説していきます。
骨董品の真の価値は、深い知識がなければ正しく判断するのが難しいものです。所有する刀について、「刻まれた印に価値はあるのか」「印がなければ価値が下がるのか」と疑問を抱く方もいるでしょう。
そこで今回の記事では、日本刀の銘について13パターンを詳しく解説します。参考にしていただければ、印の種類や刀の価値について想像していただけるはずです。
日本刀の高価買取なら美観堂にお任せください!
買取方法・買取相場・相見積もりの依頼はこちらのバナーをクリック目次
日本刀における銘とは?

日本刀における「銘」とは、茎(なかご)に入れられた文字のことです。天皇を中心とした中央集権体制のもとで銘の記載が義務化され、刀工の人名が茎に刻まれるようになりました。これは、絵画や陶器における落款と同様の役割を果たします。制作期間が印として入っているケースもあります。
茎とは柄の中に収める部位のことです。柄に収められる茎は研がれることがありません。そのため長きにわたって印が残ることから、茎にしるされるようになったとされています。
銘と号の違い
「銘」と「号」の違いは、刀を作った人の人名であるか否かであると言えます。
銘には、刀工の人名が刻まれるのが一般的です。対して号は、刀を作った人の人名とは限りません。所持者の人名、切れ味、形状、できばえがしるされることもあります。たとえば「厚藤四郎」は、一般的な刀よりも厚みのある形状をしていたことから、そのように名付けられました。石田三成が愛用していた短刀には「石田正宗」との号がつけられました。
以上のように銘は多くの場合で刀を作った人の人名であるものの、号は刀の性質や形状、持ち主に由来することが多いと言えるでしょう。したがって号は刀を作った人の人名ではありません。
基本情報を記載した日本刀の銘の種類

刀にしるされる印は、ほとんどの場合で刀を作った人の人名であると解説しました。しかしその他の基本情報がしるされることもあります。それではどのような情報がしるされることがあるのか、5つの種類について見ていきましょう。
種類1:制作した人物銘
まず代表的なのは制作した人物の人名が入れられた制作した人物銘です。刀を作った人によって印を入れる場所や書体は違います。タガネを切る方法、盛り上がり方なども作品によって異なります。刀工によっては銘の彫りが拙い場合もあり、逆に精緻な銘が刻まれていれば、別人による偽銘の可能性もあると判断されます。
制作した人物銘は、刀を作った人が持つ文字の癖が現れやすい印です。そのため、真贋を見極めるための重要な要素ともなり、刀の価値を判断するうえでの重要な基準とされます。
種類2:受領銘
朝廷から任命された地方官の官職名が刻まれたものが「受領銘」とされています。江戸時代には刀を作った人が官位を授かることも珍しくありませんでした。実際の任官を伴わない名目的な位であるものの、刀を作った人の人名の上にくにのつかさの名を付けて印をつけた当時の刀は多く見られます。「守」「大掾」「介」などが入っていれば受領銘かもしれません。
受領銘が刻まれた刀は、現代で言うブランド品のような扱いを受けており、受領を受けた刀を作った人の刀には高い価値が付けられていたとされます。
種類3:所持銘
刀の所有者の名前が刻まれた銘のことを指します。たとえば刀を注文した人がいたとしましょう。発注時に自身の名前を入れてもらえば、それは所持銘が刻まれた刀とされます。現代で言えば、オーダーメイドのネーム入れのようなものです。
人物の人名だけでなく、刀を持つ由来をともに記したケースもありました。また、いわゆる中古品の刀が他の人物に譲られた際に、新たな所有者が自身の銘を刻んだ例もあります。
室町時代、江戸時代末期の刀によく見られます。
種類4:年紀銘
「年紀銘」とは、刀が制作された年月日を刻んだ銘のことです。制作した人物銘の裏にしるされることが多くあります。年号のみが刻まれる例もありますが、年月日まで詳細に刻まれている場合も。ただし慣例であるためしるされることもあったため、正確な制作日ではないかもしれません。
種類5:依頼者の名前
依頼者の名前銘とは、刀を注文した人物と刀工の名前がともに刻まれた銘を指します。
現在でも「大量生産」と「オーダーメイド」の2種類がありますが、依頼者の名前が入った日本刀はいわば「オーダーメイド」。大量生産される刀もありましたが、依頼者の名前が入っている日本刀は注文を受けて、注文者のために特別に制作された刀であることを示しています。
2つの人名がしるされていたら、依頼者の名前である可能性が高いでしょう。
関連記事:日本刀の名刀一覧に名を連ねる天下五剣・天下三作の特徴について
磨上げた日本刀の銘の種類

刀の中には「磨上げ」が行われたものもありました。磨上げとは茎尻から切り詰めて、刀の本体を短くする処理のことです。たとえば身長や腕の長さにあわせたり、戦いの変化に対応するために磨上げが行われました。
磨上げた刀の印は一般的なものと区別されています。磨上げた刀の銘の種類について見ていきましょう。
種類1:折返銘
「折返銘」と呼ばれるのは、裏側に向けて折り返すように入れられた印です。刀の本体を短くすると印がなくなってしまうことがあります。銘が見えなくなってしまうことを避けるため、印の部分を折り返すような形でしるされたのが折返銘です。茎を裏返すことにより印を残しました。
折返銘の特徴として、銘を折り返す構造上、文字の上下が逆になる点が挙げられます。文字が反対になっていて、刀の本体の短い刀にしるされている印は折返銘であると判断できるかもしれません。
種類2:短冊銘・額銘
「短冊銘・額銘」とは、磨上げ後の茎に再びはめ込まれた銘を指します。ひとつ前の項目で折返銘について解説しました。しかし中には、折り返したとしても印を残せないケースもありました。
そこで考案されたのが短冊銘や額銘と呼ばれる印です。印の部分を短冊形に切除して、磨上げた後の茎にはめ込むことで印を残します。つまり、一度切り取られた銘を再度装着する形式のものです。
短冊形の印をはめ込んでいて、枠状に見えることから「短冊銘」あるいは「額銘」と称されます。
鑑定による日本刀の銘の種類

銘が刻まれていなかった日本刀にも、後に銘が追加された例があります。銘が刻まれていない刀の鑑定を行った本阿弥家が、安土桃山時代以降に銘入れた刀が該当します。つまり制作された段階では銘がしるされていなかったものの、その後の判定により価値が定められた刀です。これらの銘には、三つの形式があります。
種類1:金象嵌銘
金もしくは銀で入れた印のことを「金象嵌銘」と呼びます。本阿弥家が価値を判断した刀である証であるともされており、金もしくは銀によって印がしるされていることが特徴です。金で刻まれたものは「金象嵌銘」、銀で刻まれたものは「銀象嵌銘」と呼ばれます。磨上げをした刀を作った人の人名、所持者銘、価値を判断した人の名前が銘としてしるされているケースが多く見られます。
種類2:朱銘
「朱銘」は金もしくは銀での銘と同じように、本阿弥家が価値の判断を行った銘のない刀の中でも、朱漆で入れられた印のことを指します。彫刻を施さず朱漆を塗布する形式のため、茎を傷つけることはありません。一般的には表側に刀を作った人の人名がしるされており、反対側には、鑑定を行った人物の名前や花押が添えられました。
茎の部分に朱色の印があれば、本阿弥家が判断を行い朱銘を入れた刀であると考えて良いでしょう。
種類3:金粉銘
朱漆の代わりに、漆に金の粉末を混合させたものでしるされたのが「金粉銘」。本阿弥家が価値の判断を行って入れた印であること、茎が傷つかないことは朱銘と同じで変わりはありません。朱銘と同じように刀を作った人名、価値を判断した人の名前、花押がしるされているケースが多く見られます。
金粉銘が施された刀を扱う際は、銘が消失しないよう注意が必要です。摩擦によって銘が消える恐れがあるため、柄からの出し入れ時には細心の注意が求められます。
切れ味を記載した日本刀の銘の種類

続いては、切れ味が記された日本刀の銘の種類について解説します。最初に、刀の印には切れ味がしるされていることもあると解説しました。切れ味についての印にはどのようなものがあるのか、一例を見ていきましょう。
試し銘・裁断銘
「試し銘」もしくは「裁断銘」とは、試し切りの結果に基づいて刻まれた銘を指します。試し切りをしてどのような切れ味であったかがしるされます。当時の試し切りでは、罪人の身体が使われることも少なくありませんでした。そこで試し銘や裁断銘には、どの部分をどれだけ切って、どのような切れ味であったかがしるされていることが多いでしょう。
江戸時代初期の刀に多く見られる印であり、刀の切れ味を証明します。これを読み解くことで、その刀がどの程度の切断能力を備えていたかを知る手がかりとなります。
無銘の日本刀が存在する理由

解説いたしましたように、刀の中には印が入っていない「無銘の刀」が存在します。天皇を中心とした中央集権体制の確立により、銘の刻印が制度として義務付けられました。しかし天皇中心の中央集権国家体制確立以降も、印が切られていない作品が制作されたことは事実です。それではなぜ無銘の日本刀が存在するのか、3つの理由を見ていきましょう。
理由1:あえて銘を切らなかったため
まず刀を作った人が「あえて入れないようにした」ことが理由として考えられます。刀は戦いに使用するためだけに制作されたのではありません。神社仏閣や身分の高い人物に納めるために制作されたこともありました。位の高い相手に献上するために制作された刀に銘を刻むことは、相手に対して無礼と受け取られる可能性がありました。そのためあえて入れないようにした奉納や献上のために制作された刀である可能性が考えられるでしょう。
理由2:わざと削ったため
もともとしるされていた印を、人が削ってなくすケースも見受けられます。印が入っていなければ、「名工が制作した無銘の刀」として販売できるためです。つまり銘を意図的に削ることで、名工の作と偽って高値で売却する例も見受けられます。
そのほか、災いをもたらす妖刀として名高い「村正」は、徳川家康が嫌っていたことから、当時においても村正の銘が削られていました。さまざまな理由から、印を削ってなくすこともあります。
理由3:茎を短く切り詰めたため
茎を短く詰めた結果、銘が失われた刀も存在します。古い刀は非常に長尺で、実用には不便とされたため、制作後に本体を短くした刀の中には、印がしるされた部分がまるごと失われてしまったものも。より扱いやすいように、刀の本体を短くされたケースがありました。もともと銘が刻まれていた部分が削られたことで、その後は「無銘の日本刀」として扱われるようになりました。
日本刀の価値を判断するには銘の知識を
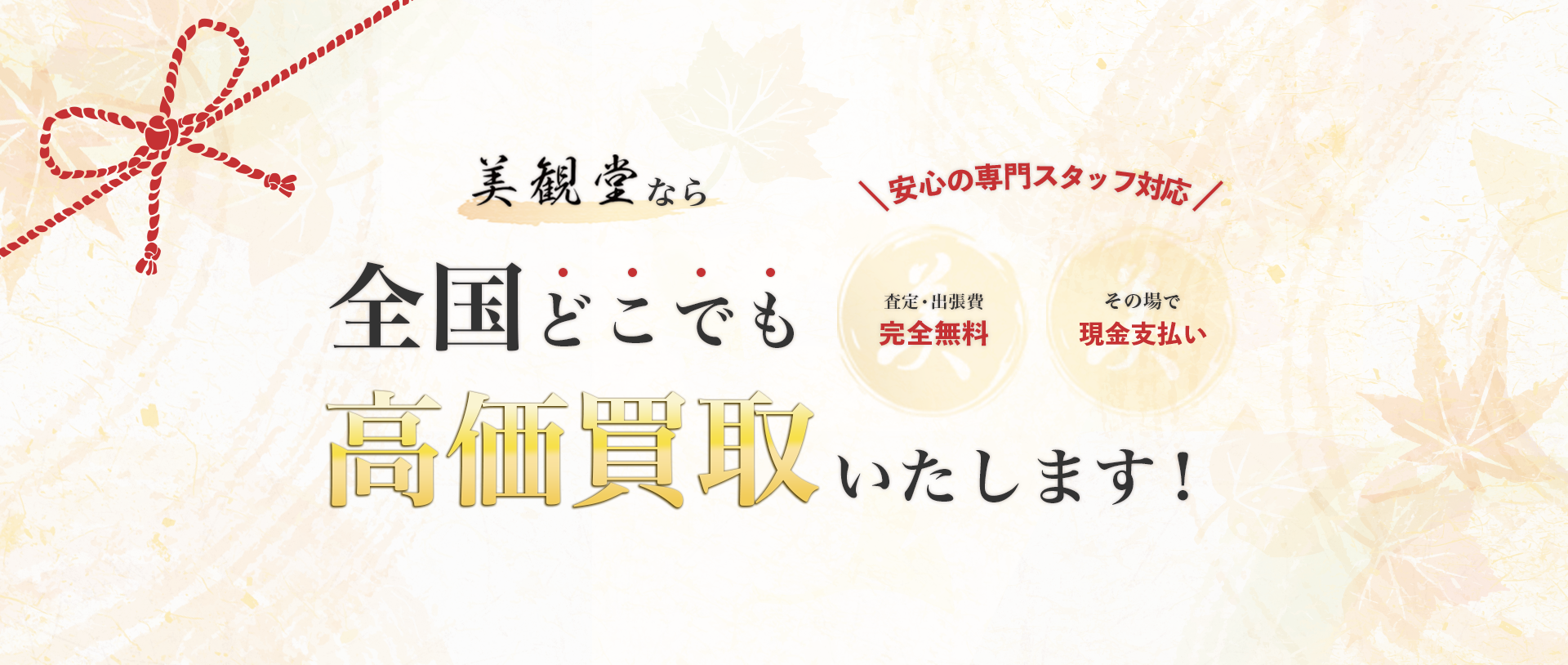
いかがでしたでしょうか?この記事を読んでいただくことで、日本刀の銘に関する理解が深まったのではないでしょうか。
日本刀の銘は刀を作った人や所持者、切れ味などを証明するもの。価値判断の基準のひとつとなるため、知識を備えておきたいものです。
美観堂では専門スタッフの鑑定眼により、印のない日本刀でも適切な鑑定を行っております。専門的な視点から適正価格での査定をご提示いたしますので、銘を切ってある作品・無銘の作品のいずれでも、日本刀・刀剣の買取なら美観堂の無料査定をお試しください。
この記事の監修者

義村 安悟(よしむら あんご)
《経歴》
美観堂 大阪本店店長 査定歴15年
《コメント》
複数の店舗で店長としての経験を活かし、身の回りのさまざまなジャンルのお品物を丁寧に査定しています。特に古美術品の買取においては、作品の歴史や芸術的価値、作家や時代の背景を考慮して査定を行っており、状態だけでなく市場の動向を踏まえ、公正で適正な価格設定を心がけております。
また、遠方にお住まいのお客様からのご依頼も多い中、出張買取を通じて、さらにお役に立てるよう努めてまいりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。《許可証》
古物商営業許可番号:第62111R051143号
美観堂買取
〒542-0062大阪府大阪市中央区
上本町西5丁目3-3ワンダー5ビル1F
選ばれる理由
|
|
|
|


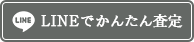
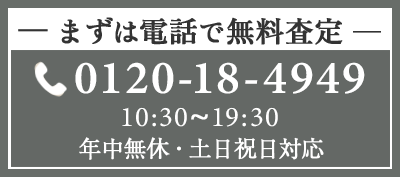





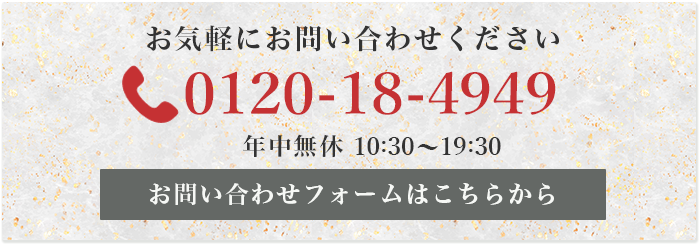



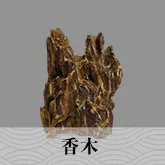
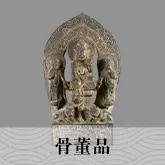


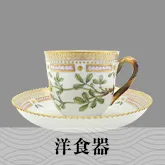
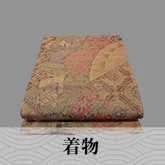
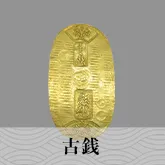



 査定・出張費無料
査定・出張費無料 キャンセル無料
キャンセル無料 安心・信頼
安心・信頼 丁寧・迅速
丁寧・迅速