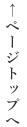コラム
-
骨董品について
富本銭・和同開珎の違いと富本銭が最古の貨幣と考えられている理由
公開日 2025/04/21
更新日 2025/04/30
-

富本銭(ふほんせん)と和同開珎(わどうかいちん(ほう))は、飛鳥時代から奈良・平安時代にかけて作られた貨幣です。両貨幣の違いがわからず、困っている方もいるでしょう。富本銭と和同開珎を比較すると、発行された年代や発行の目的などが異なります。
ここでは、これらの違いを解説するとともに、富本銭が最古の貨幣と考えらえている理由、両貨幣の買取価格の目安を紹介しています。理解を深めたい方は参考にしてください。
古銭の高価買取なら美観堂にお任せください!
買取方法・買取相場・相見積もりの依頼はこちらのバナーをクリック目次
富本銭と和同開珎の違いとは?

富本銭と和同開珎のおもな違いは以下のとおりです。
発行された時代
富本銭は、飛鳥時代(683年)に唐の銅銭「開元通宝(621年発行)」をモデルとして作られました。発行された時代を示す根拠のひとつといえるのが、飛鳥池工房遺跡で富本銭が大量に出土したことです。同じ地層から、7世紀後半に作られたことを確認できる木簡、瓦なども見つかっています。
和同開珎は、奈良・平安時代(708年)に「開元通宝」をモデルとして作られました。和同遺跡で和銅が見つかったことを記念して、元号を和銅に改めるとともに和同開珎が作られたと考えられています。ちなみに、和同開珎は日本で鋳造した12種類の銅銭「本朝十二銭(または皇朝十二銭)」のひとつ目にあたります。
関連記事:寛永通宝とは?歴史・種類・価値などを解説
発行の目的
富本銭の発行目的は、はっきりとわかっていません。現在のところ以下の説が有力視されています。
目的 概要 流通貨幣説 国家構想事業の支払い手段などとして用いられた。飛鳥池工房遺跡から大量に出土したため有力視されている 厭勝銭説 まじない用の銭として用いられた。飛鳥池工房遺跡から大量に出土するまでの定説だった 統治理念の表現説 国家を象徴する貨幣として発行された 出典:(pdf)奈良県立万葉文化館「天武・持統・文武天皇の富本銭発行」
和同開珎は、流通貨幣として発行されました。具体的には、平城京の造営工事に充てる費用を捻出するため作られたと考えられています。
発行当時の価値
発行当時における富本銭の価値はわかっていません。取引に関する記録などが見つかっていないためです。それほど普及しなかったことも影響しているでしょう。広く受け入れられなかった理由は、それまで用いられていた無文銀銭が地銀価値で流通していたためです。地銀価値の低い銅を使用していた富本銭は、歓迎されなかった可能性があります。和同開珎は1文として通用しました。1文の価値は米1升2合(約1.8kg)程度、あるいは造営工事における1日の労賃です。その後、和同開珎の価値は低下し、736年頃には土器の椀2個程度の価値になったことがわかっています。
出典:京都国立博物館「無文銀銭と和同開珎―日本最古のコイン―(むもんぎんせんとわどうかいほう(ちん)―にほんさいこのこいん―)」
材質
富本銭は、銅とアンチアモンを用いた特殊な合金を使用しています。アンチアモンは、銀白色で半金属の個体です。当時の技術を用いて復元した富本銭は、金色味を帯びた淡い銅色をしています。美しい輝きを放つ貨幣だったといえるでしょう。和同開珎の素材は、銅、鉛、アンチアモン、錫を用いた合金です。和同開珎は精巧さに欠ける古いものと精巧なものにわかれます。前者はアンチアモン、後者は鉛と錫を多く含みます。
形状
富本銭の形状は以下のとおりです。
【形状】
- 直径:24mm
- 厚さ:1.3mm程度
中心に四角い穴(方孔)が開けられており、上下に「富」と「本」の文字、左右に七曜文が描かれています。「富」と「本」の文字は、芸文類聚(げいもんるいじゅう)に登場する「富民之本、在於食貨」に由来すると考えられています。「民を富ませる本は、食と貨幣にある」という意味を持ちます。
出典:高森町歴史民俗資料館 時の駅「日本最古の銅製鋳造貨幣『富本銭』」
和同開珎の形状は以下のとおりです。
【形状】
- 直径:24mm程度
- 厚さ:1.5mm程度
中心に四角い穴(方孔)が空いていて、時計回りで「和同開珎」の文字が描かれています。安らぎを表す「和同」と、初めてのお金を意味する「開珎」という語から構成されています。
発見された時代
富本銭は、江戸時代には、すでにその存在が記録されていました。古銭を収録した本に、富本七星銭の名称で掲載されていたためです。実際に発見されるまで、江戸時代に作られたものと推定されていました。その実物が確認されたのは1985年のことです。平城京跡で、和同開珎などとともに見つかりました。その後、藤原京跡、難波京跡、飛鳥池遺跡などでも出土しています。
和同開珎は、さまざまな地域で見つかっています。一例としてあげられるのが、1957年(昭和32年)に三子牛町(金沢市)の道脇で採集された545枚の和同開珎です。1981年(昭和56年)には、米子市の諏訪西山ノ後遺跡でも見つかっています。この際に発見された和同開珎は3枚でした。
富本銭が日本最古の貨幣だとされる理由とは?

富本銭は、日本最古の貨幣と位置づけられており、教科書にもそのように記載されています。このように考えられている理由は、天武天皇(在位673年から686年)が都を置いていた地域にある飛鳥池遺跡から未製品の富本銭が大量に出土したためです。また、同じ地層で7世紀後半のものと確認できる木簡なども見つかっています。これらの出土状況から、富本銭は7世紀後半に鋳造されたと推定され、日本最古の貨幣とされています。
富本銭と和同開珎の買取価格

富本銭と和同開珎の買取価格は以下のとおりです。
種類 買取価格の目安 富本銭 不明 和同開珎 数千円~数百万円程度 富本銭は、希少性が非常に高い貨幣です。参考となる事例が乏しく、買取価格の目安を提示するのは困難です。テレビ東京の番組「開運!なんでもお宝鑑定団」では、1,000万円の評価が出た事例もあります。
和同開珎の買取価格は種類で大きく異なります。流通量が多い銀銭は、数千円から数万円で取引される例が一般的です。一方で、三ツ跳、四ツ跳と呼ばれている和同開珎(文字に跳ねのある書体を持つ種類)は、120万円~250万円程度で取引されています。
富本銭と和同開珎は異なる貨幣
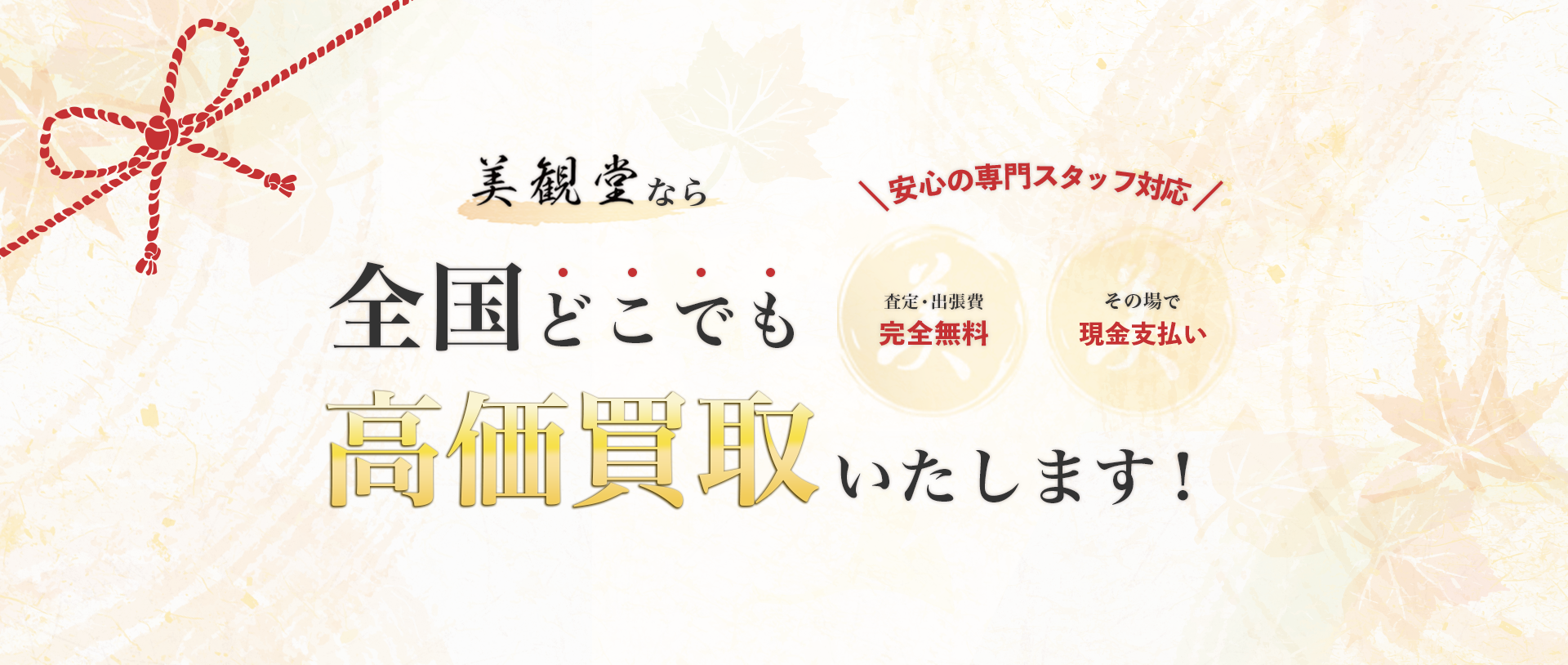
ここでは、富本銭と和同開珎の違いを解説しました。富本銭は683年、和同開珎は708年に、開元通宝を基に鋳造された貨幣とされており、いずれも流通を目的として鋳造されたと推定されています。ただし、富本銭は、まじないに使用された可能性などがあります。両者には、高い価値が認められているという共通点があります。
手元に富本銭、和同開珎がある方は、古銭の買取なら美観堂にお任せください。
業界歴15年以上の鑑定士が、経験に基づいた適切な査定を提供しています。この記事の監修者

義村 安悟(よしむら あんご)
《経歴》
美観堂 大阪本店店長 査定歴15年
《コメント》
複数の店舗で店長としての経験を活かし、身の回りのさまざまなジャンルのお品物を丁寧に査定しています。特に古美術品の買取においては、作品の歴史や芸術的価値、作家や時代の背景を考慮して査定を行っており、状態だけでなく市場の動向を踏まえ、公正で適正な価格設定を心がけております。
また、遠方にお住まいのお客様からのご依頼も多い中、出張買取を通じて、さらにお役に立てるよう努めてまいりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。《許可証》
古物商営業許可番号:第62111R051143号
美観堂買取
〒542-0062大阪府大阪市中央区
上本町西5丁目3-3ワンダー5ビル1F
選ばれる理由
|
|
|
|


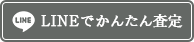
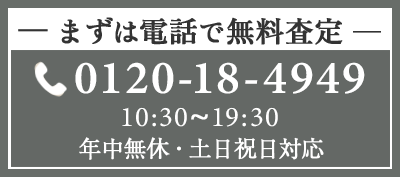





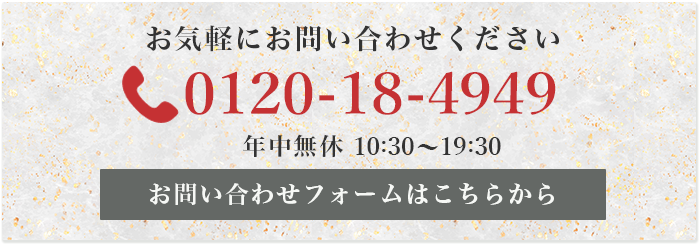



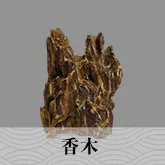
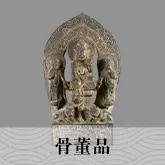


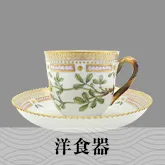
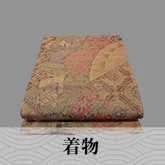
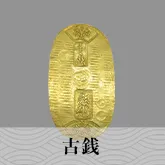



 査定・出張費無料
査定・出張費無料 キャンセル無料
キャンセル無料 安心・信頼
安心・信頼 丁寧・迅速
丁寧・迅速