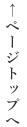コラム
-
刀(打刀)と太刀の違い|違いが生まれた背景とそれぞれの魅力
公開日 2025/04/18
更新日 2025/04/30
-

日本刀は「刀(打刀:うちがたな)」と「太刀」に大別されます。両者の違いがわからず困っている方もいるでしょう。刀は室町時代以降、太刀は平安時代から室町時代初期にかけて日本国内で作られた刀剣です。両者を比較すると、長さや反りの深さなどに違いがあります。
本記事では、刀と太刀の概要を解説するとともに、両者の違い、魅力、両者を見分ける際の注意点などを紹介しています。刀と太刀の違いが気になる方は参考にしてください。
日本刀の高価買取なら美観堂にお任せください!
買取方法・買取相場・相見積もりの依頼はこちらのバナーをクリック目次
刀とは?

おもに室町時代以降に作られた刀剣を指します。いわゆる「侍」が腰に差していた、大ぶりの刀を指すと考えられます。外見上の特徴は、刃渡り2尺3寸程度で反りが浅い点が特徴です。徒歩戦や屋内戦を想定しているため比較的短めに設計されています。右手で素早く抜刀できるよう、刃を上向きにして左腰に差す点も特徴といえます。また、実用性、機能性を優先するため、華な装飾は基本的に用いられていません。
太刀とは?

おもに平安時代から南北朝時代、あるいは室町時代初期にかけて作られた刀剣を指します。外見上の特徴は、刃渡り2尺5寸程度で反りが深いことです。太刀には、以下の種類があります。
種類 刃渡り 小太刀 2尺未満 太刀 2尺5寸程度 大太刀 3尺以上 騎馬戦を想定していたため、上記の長さになり、湾曲が大きくなったとされています。豪華な装飾が施されていた点も特徴です。鍔を含めて、デザイン性に優れたものも多く見られます。美術品としての価値も備えています。
刀と太刀の違いが生まれた背景

刀と太刀には、さまざまな違いがあります。違いが生まれた主な要因としては、時代や用途が挙げられます。前述のとおり、太刀は平安時代から南北朝時代(あるいは室町時代初期)、刀は室町時代以降に用いられました。時代が異なると、想定する戦いも異なります。平安時代から南北朝時代(あるいは室町時代初期)に想定した戦いは1対1の騎馬戦、室町時代以降に想定した戦いは集団で行う徒歩戦あるいは屋内戦です。これらの戦いに適した形へと、刀や太刀は変化していきました。
刀と太刀の違い

ここでは、両者の違いを詳しく解説します。
時代
太刀は、中国から伝来した両刃の直刀から生まれたと考えられています。平安時代後期に、主に用いられていたのが、腰反りとよばれる手元付近が強く反った太刀です。この形状は、騎馬上での抜刀がしやすいという利点があります。
時代が流れて室町時代、戦国時代に入ると、戦いの場が1対1の騎馬戦から集団で行う徒歩戦へ移りました。大勢が入り乱れて戦う徒歩戦だと、長い刀身は動きの妨げになることがありました。そこで登場したのが、刀身が短く、湾曲が浅い形状の刀です。室町時代以降は、混戦の中でも抜刀しやすい刀が使用されるようになりました。
携帯方法
それぞれの携帯方法は以下のとおりです。
種類 携帯方法 刀 刃を上向きにして左腰に差す(帯刀:たいとう) 太刀 刃を下向きにして紐で左腰に吊るす(佩刀:はいとう) 刀は、刃を上向きにして腰帯に差します。おもな理由は、鞘から素早く抜くためです。太刀は、刃を下向きにして太刀緒で腰から吊るします。太刀緒とは、この目的のために用いられた革製などの紐のことを指します。腰に差さない理由は、長さと重さがあるため、動きにくくなるなど、抜刀が難しくなるためです。なお、博物館などでも同様の向きで展示されています。両者を見分けるための手がかりの一つといえます。
反り
反りは刀身の湾曲です。日本刀が備える特徴のひとつといえます。反りのおもな役割は以下のとおりです。
【反りの役割】
- 衝撃を吸収する
- 抜刀を容易にする
- 引き切りをしやすくする
原則として、太刀は湾曲を大きく設計しています。騎馬上で鞘から太刀を抜きやすくするためです。また、湾曲が大きいと、鞘尻の位置が高くなるため、佩刀時に意図せず馬の尻を叩くことがないよう配慮されています。反対に、刀は湾曲を小さくしています。徒歩戦や室内戦での取り回しを考慮した設計です。用途の違いが形状に影響を与えたと考えられます。
刀身の長さ
刀の刀身は長さ2尺3寸程度、太刀の刀身は長さ2尺5寸程度です。センチメートルに換算すると、前者は長さ69.7cm程度、後者は75.8cm程度と考えられています。このように、刀は太刀よりもやや短く作られています。集団戦や屋内戦で扱いやすくするためです。騎馬上からの斬撃を想定している太刀は、刀よりも長く作られています。徒歩戦よりも距離のある敵を攻撃するために設計されていますが、本記事で説明している刀身の長さは、例外も多く、あくまで目安とされています。
デザイン
原則として、刀は実用性を重視しています。柄や鍔のデザインを必要最低限に抑えるなど、デザインを簡素にしているものが少なくありません。日本的な美意識を反映していると考えられています。これに対して、太刀は豪華な装飾を施している傾向があります。たとえば、鍔に金細工を施しているものもあります。豪華な装飾も太刀の特徴の一つとされています。刀剣でありながら、美術品としての価値も備えています。
価値観
太刀は、所有者の社会的地位を示すものでした。したがって、豪華な装飾が好まれたと考えられます。刀が普及すると、精神性がより重視されるようになります。帯刀そのものが、武士の誇り、鍛錬の証と考えられるようになったのです。価値観の違いも理解しておくべき点の一つといえます。
役割
太刀は、おもに騎馬上で使用された刀剣です。戦国時代以降は、大規模な徒歩戦が増えたため、実用性が低下しました。ただし、完全に役割を失ったわけではありません。貴族や武家によって、儀式などに用いられてきました。刀は、おもに徒歩での使用を想定した刀剣です。太刀より扱いやすかったため、戦国時代以降は実戦用の刀剣として用いられました。また、江戸時代に入ると、身分を象徴する役割を担います(武士階級)。武家諸法度により、帯刀が義務づけられていたためです。
関連記事:刀の部位とその名称|上身・茎・断面・拵を構成するもの
刀と太刀の違いを比較して人気なのは?

刀と太刀では、どちらが人気なのでしょうか。それぞれの魅力を詳しく解説します。
刀が選ばれる理由
戦国時代以降につくられた刀は、実戦で使用することを想定しています。実用性を追求して生まれた機能美が特徴とされています。また、実際に戦で使用されているものも少なくありません。それぞれの刀がもつ歴史を感じられる点も魅力といえるでしょう。ただし、刀身の状態は査定結果に影響を与えます。傷や錆が目立つなど、劣化が進んでいるものは注意が必要です。太刀と比べた場合、保管しやすさも強みになりえます。刀身が短く、重さも軽いためです。大きなスペースを必要としないため、飾りやすいという利点もあります。現在の住環境にも適した刀剣といえます。
太刀が選ばれる理由
太刀に見られる豪華な装飾も特徴の一つとされています。刀身の美しさはもちろん、柄、鍔、鞘の装飾も見逃せません。細部にまでこだわった意匠は、美術品や芸術品としての価値も認められています。刀身の長さも、強みと考えられます。展示したときに、迫力を感じられるためです。また、太刀の多くは、平安時代から伝わる優雅さや気品を備えているとされています。歴史に裏打ちされた品位を感じられる点も魅力です。
刀と太刀の違いを見分ける際の注意点

反りの深さや長さのみで明確に区別することはできません。判断に迷う場合は、銘の位置に注目するとよいでしょう。銘は、茎(かなご・柄におさめられる持ち手部分)に打たれた刀工の名前などです。原則として、帯刀または佩刀したときに外側にくるように銘を切っています。具体的には、以下のとおりです。
種類 銘の位置 刀 刃を上向きにして左腰に差したときに刀工の名前が外側(差表)にある 太刀 刃を下向きにして左腰に吊るしたときに刀工の名前が外側(佩表)にある ただし、太刀の中には、反対側に銘を切っているものもあります。絶対的な基準ではない点に注意が必要です。一定の知識を身につければ、刃文などから見分ける力を身につけることができます。
刀と太刀では作られた年代が異なる
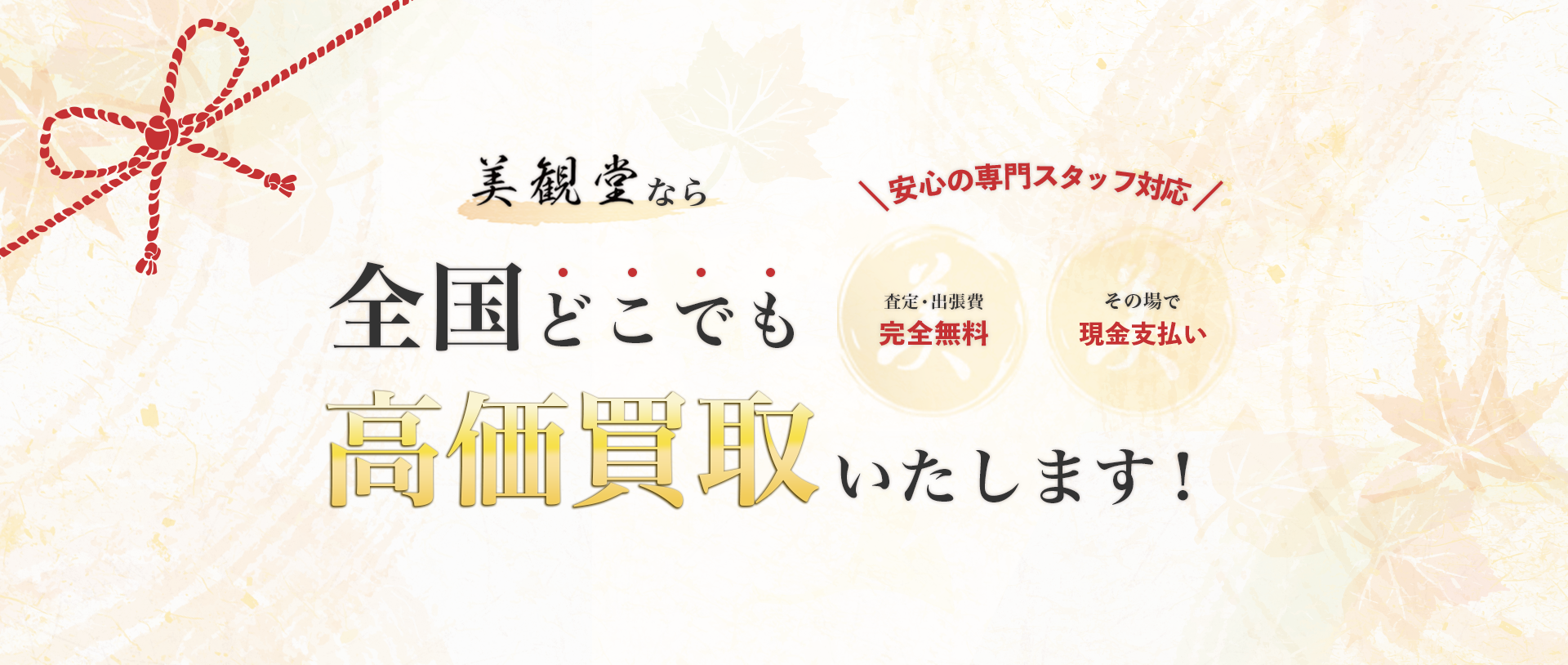
ここでは、刀と太刀の違いについて解説しました。前者はおもに室町時代以降、後者はおもに平安時代から室町時代初期にかけて作られた刀剣です。戦の在り方が変わったため、長さや反りなどに違いが生じました。刀の特徴は、実用性を追求した機能美、太刀の魅力は豪華な装飾を施しているものが多いです。それぞれの特徴を理解したうえで鑑賞することが大切です。不要になった日本刀の売却を検討している方は、業界歴15年以上の専門家が査定を行っています。日本刀・刀剣の買取なら美観堂にお任せください。
この記事の監修者

義村 安悟(よしむら あんご)
《経歴》
美観堂 大阪本店店長 査定歴15年
《コメント》
複数の店舗で店長としての経験を活かし、身の回りのさまざまなジャンルのお品物を丁寧に査定しています。特に古美術品の買取においては、作品の歴史や芸術的価値、作家や時代の背景を考慮して査定を行っており、状態だけでなく市場の動向を踏まえ、公正で適正な価格設定を心がけております。
また、遠方にお住まいのお客様からのご依頼も多い中、出張買取を通じて、さらにお役に立てるよう努めてまいりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。《許可証》
古物商営業許可番号:第62111R051143号
美観堂買取
〒542-0062大阪府大阪市中央区
上本町西5丁目3-3ワンダー5ビル1F
選ばれる理由
|
|
|
|


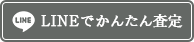
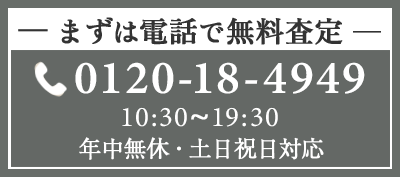





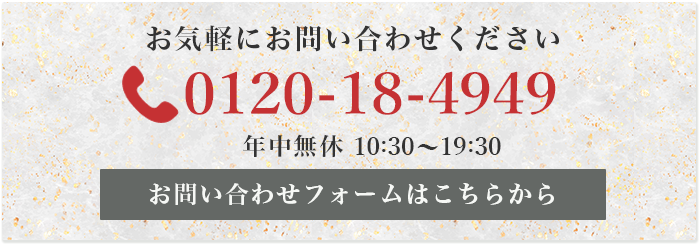



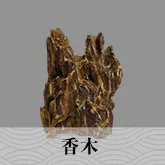
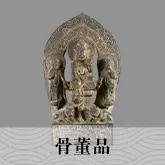


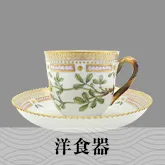
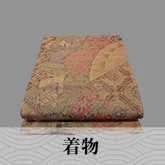
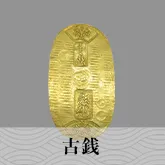



 査定・出張費無料
査定・出張費無料 キャンセル無料
キャンセル無料 安心・信頼
安心・信頼 丁寧・迅速
丁寧・迅速