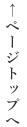コラム
-
「銃砲刀剣類登録証」とは?取得の流れと紛失したときの対処法
公開日 2025/04/18
更新日 2025/04/30
-

銃や刀剣をコレクションアイテムや古美術品として所有する場合は、銃砲刀剣類所持等取締法に基づき登録を受ける必要があります。
この法律は、美術品や骨董品として価値があると認められたものを例外的に所持できるように認めるもので、取引の際にも認定を受けていることが重視されます。
ここでは、認定の際に発行される銃砲刀剣類登録証について、取得の流れや手続きに関する詳しい内容を紹介します。登録証の所有者が変わる場合と変わらない場合の手続きについても詳しくみていきましょう。
日本刀の高価買取なら美観堂にお任せください!
買取方法・買取相場・相見積もりの依頼はこちらのバナーをクリック目次
銃砲刀剣類登録証とは?

鉄砲や刀剣を所持する場合、銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)に基づく正式な登録が必要です。
登録証は認定を受けることで正式に発行されます。登録証を持たずに鉄砲や刀剣を所持・売買・取引すると、違法行為として処罰の対象となります。
登録証には種別(刀や鉄砲など)や対象物のサイズ・口径、銘文(ある場合)などが記載されます。紛失した場合でも、再発行の手続きが可能です。
銃砲刀剣類登録証は1点ごとに発行され、登録記号番号が記載されています。登録証の発行日や、どの教育委員会が発行したかといった情報も印字されています。
所有者が変更された場合は、所定の手続きを行う必要があります。
銃砲刀剣類登録証取得の流れ

銃砲刀剣類登録証を取得する流れは次のとおりです。
【警察署への届け出】
刀剣や銃砲を所有、または発見したときには、最寄りの警察署の生活安全課に連絡します。後日「刀剣類発見届」を署に提出し、「刀剣類発見届出済証」を受け取りましょう。
これらの手続きは刀剣や鉄砲の発見者自身またはその家族が行います。
【登録審査会への参加】
警察署から都道府県の教育委員会に連絡されると、登録審査会への案内が届きます。審査会とは、骨董品や美術品としての価値があるかどうかを判断する場です。
日時と場所は指定されており、所定の機関が審査を実施します。一例として、北海道エリアでは「北海道教育委員会生涯学習推進局文化財・博物館課」が審査を担当します。
当日は、登録を希望する刀剣・鉄砲と刀剣類発見届出済証を持参してください。
審査会に到着すると、刀剣類に正しい知識をもつ審査員が長さや反りといった細部をチェックします。問題がなければ、その場で審査を通過します。
【登録証の発行】
審査に通ると、その日のうちに銃砲刀剣類登録証が発行されます。手数料を1点ごとに支払うことで、審査会は完了します。
こうして、法的にも所有や取引が認められたことになり、刀剣や銃砲を合法的に所持・売却することが可能になります。
銃砲刀剣類登録証の所有者が変わる場合の手続き

銃砲刀剣類登録証の所有者が変更になったときは、所定の手続きを行わなければなりません。手続きを済ませなければ古い所有者の名義のままとなり、本人不在の状態で取引や売却を行うことはできません。
ここからは、日本刀を相続したとき・日本刀を新たに購入したときについてみていきましょう。
日本刀を相続したとき
日本刀を親族などから相続したときは、すぐに所有者変更手続きを行います。被相続人の名義のままでは所有や売買ができないため、新たな相続人の名義に変更します。
相続人は、銃砲刀剣類登録証に記載されている都道府県の教育委員会に所有者変更届を持参・郵送・電子申請します(※)。
都道府県の公式ホームページから所有者変更届がダウンロードできますので、印刷して必要事項を記入してください。
譲渡または相続を選択する欄があります。譲り受けている場合は譲渡に該当し、親族などから相続した場合は、相続の欄にチェックを入れてください。
※申請方法は都道府県によって異なるため要問い合わせ
銃砲刀剣類登録証がある場合
銃砲刀剣類登録証が手元にある場合は、登録証を発行した都道府県の教育委員会へ所有者変更届を行います。
登録証を確認しながら、記載されている内容を正確に転記します。ここでは元の所有者の住所・氏名と、相続人の住所・氏名がそれぞれ求められるため、間違いのないように記入しましょう。
銃砲刀剣類登録証がない場合
銃砲刀剣類登録証が手元にない場合や、紛失・破損した場合は、再交付の手続きが必要です。
再交付を受けるためには、最寄りの警察署に連絡します。後日、銃砲刀剣類登録審査会へ刀剣を持参し、現物を確認したのち、登録証が再交付されます(再交付手数料が必要です)。
登録証は、公的に所有を認める証明書です。登録証がなければ、刀剣を所有することは認められていません。必ず手続きを経て再交付を受けるようにしてください。
日本刀を新たに購入したとき
日本刀を購入したときは、銃砲刀剣類登録証が付帯されていることを確認してください。
登録証が付属している場合は、購入日から20日以内に所轄の都道府県の教育委員会へ所有者変更届出書を提出する必要があります。店舗によっては印鑑を持参することでその場で所有者変更届出書の作成ができます。
登録証がない場合は、速やかに登録証の交付手続きを行う必要があります。最寄りの警察署の生活安全課に連絡し、後日「刀剣類発見届」を署に提出して「刀剣類発見届出済証」を受け取り、都道府県の教育委員会で審査を受け、正式な登録証の発行を受けます。
関連記事:日本刀の名前の由来とは?種類ごとの名付けと知名度の高い刀について
銃砲刀剣類登録証の所有者が変わらない場合の手続き
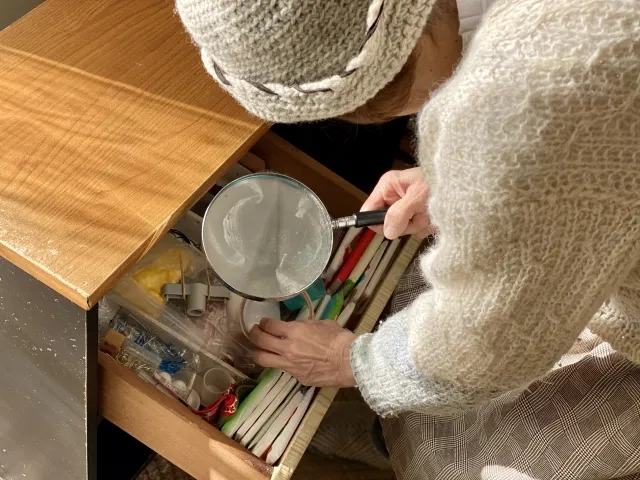
銃砲刀剣類登録証の所有者が変わらない場合は、どのような手続きが必要になるのでしょうか。
所有者が住所を変更した場合、および登録済みの日本刀に手を加えた場合の手続きについて確認します。
所有者が住所変更したとき
同じ所有者が転居などを行って新住所に引っ越した場合は、登録証を発行した都道府県に住所変更届を提出してください。
各都道府県の公式ホームページでは、所有者変更届とは別に住所変更届と呼ばれる書式が用意されています。ダウンロードし必要事項を記入して電子申請を行うか、登録証のコピーを添付してメールで送付します。
電子申請に対応していない都道府県では、メール送信または郵送のいずれかで提出します。
所有者が登録されている日本刀に手を加えた場合
所有している日本刀に彫刻や銘を入れる、磨き上げによる反りの変化がみられるなど、登録されている日本刀に手を加えた場合は、新たに登録をし直さなければなりません。
再登録が必要な理由として、登録証に記載された情報と現物の状態が一致しなくなるためです。手を加えた場所や内容を明確にしたうえで、新たに登録証の交付を受けます。
注意点として、日本刀に手を加える前に所轄の教育委員会へ申告しましょう。そして、変更前後の日本刀の状態を示す写真や押形を取得し、保管しておきましょう。
日本等に手を加えた後は、都道府県の教育委員会のホームページにある申請書類をダウンロード・記入し、写真・押形と共に郵送します。後日、審査会で登録審査が行われると、新しい登録証が発行されます。
新しい登録証の発行に伴い、旧登録証の返納が求められます。また、新規登録では登録審査手数料が必要です。
銃砲刀剣類登録証を紛失した場合の手続き

銃砲刀剣類登録証を紛失した場合は、速やかに再交付の手続きを行ってください。
はじめに登録証を発行した都道府県の教育委員会へ連絡し、再交付申請を希望していることを伝えます。必要書類についての説明があり、後日郵送される書類またはホームページから書式をダウンロードして印刷し、必要事項を記入のうえ返送します。
登録証が亡失または盗難にあった場合は、所轄の警察署へ遺失物届を提出してください。遺失物の届け出では受理番号が発行されるので、教育委員会に返送する書類にもこの受理番号を記入します。
状況に応じて、「亡失」「盗難」「滅失」のいずれかに分類されます。亡失は登録証そのものを失くすことですが、滅失とは、登録証が破損したり、文字が薄くなって判読できなくなった状態を指します。
所有や売却には銃砲刀剣類登録証が必要
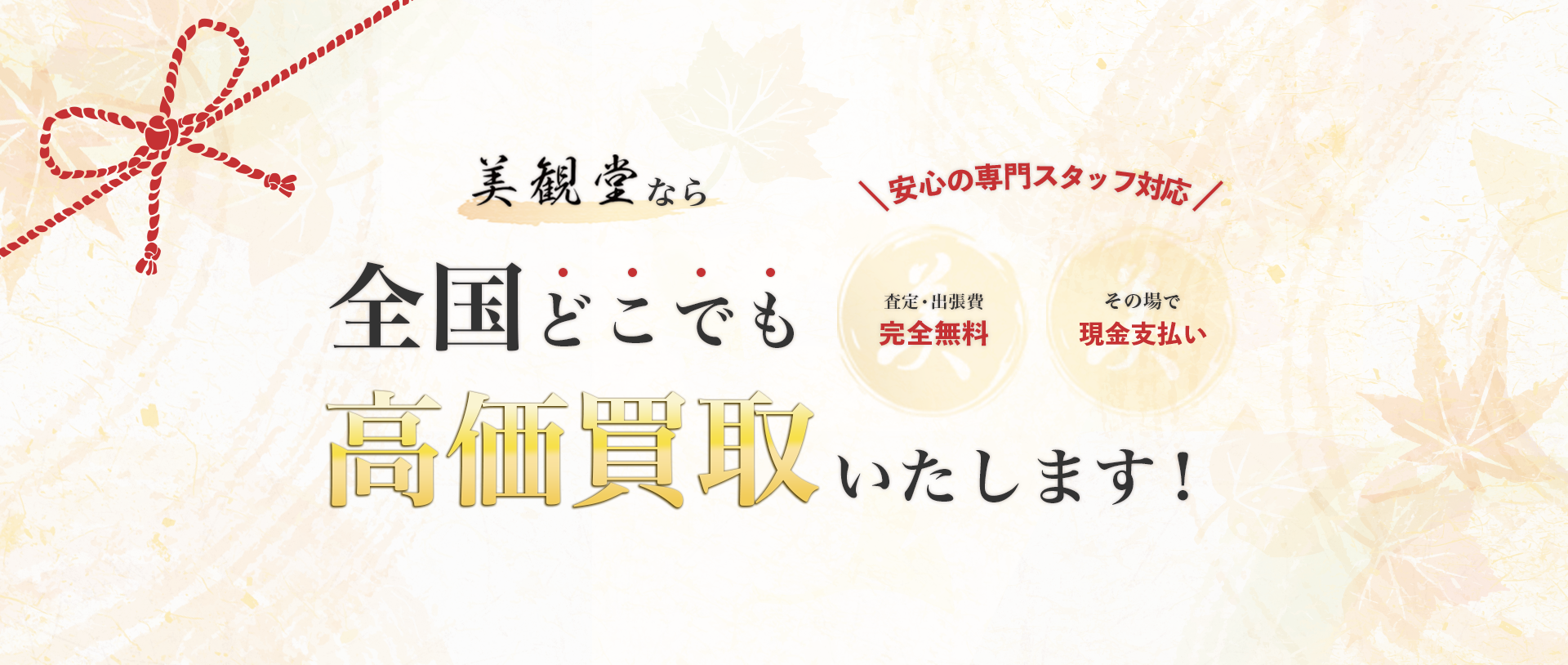
今回は、銃砲や刀剣の所有・取引に必要な銃砲刀剣類登録証について紹介しました。
日本刀の購入・譲渡・相続などの際には、銃砲刀剣類登録証が必要です。登録証がなければ所有が認められないため、名義人や住所を最新の状態に保ち、正しい手順で登録手続きを行う必要があります。
日本刀・刀剣の買取なら美観堂にお任せください。当店では、査定料無料で日本刀や刀の買取、古銭やお札の買取を行っています。出張・持ち込み・宅配による買取に対応しており、LINE査定にも対応しています。鑑定書や登録証が付属している日本刀・刀剣も取り扱っておりますので、この機会にぜひご相談ください。
この記事の監修者

義村 安悟(よしむら あんご)
《経歴》
美観堂 大阪本店店長 査定歴15年
《コメント》
複数の店舗で店長としての経験を活かし、身の回りのさまざまなジャンルのお品物を丁寧に査定しています。特に古美術品の買取においては、作品の歴史や芸術的価値、作家や時代の背景を考慮して査定を行っており、状態だけでなく市場の動向を踏まえ、公正で適正な価格設定を心がけております。
また、遠方にお住まいのお客様からのご依頼も多い中、出張買取を通じて、さらにお役に立てるよう努めてまいりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。《許可証》
古物商営業許可番号:第62111R051143号
美観堂買取
〒542-0062大阪府大阪市中央区
上本町西5丁目3-3ワンダー5ビル1F
選ばれる理由
|
|
|
|


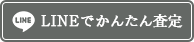
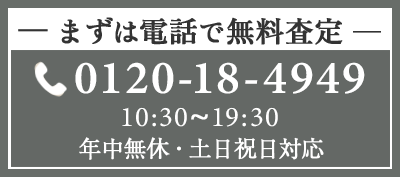





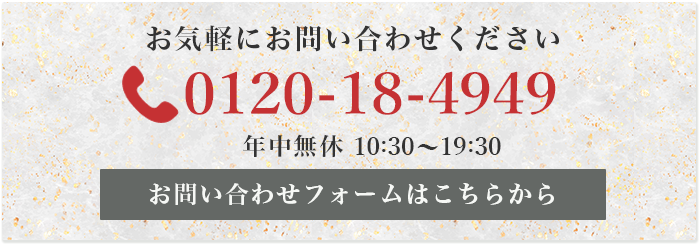



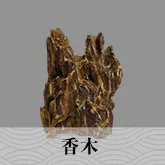
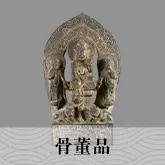


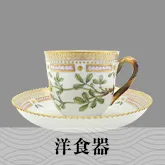
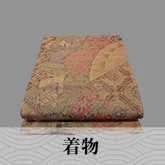
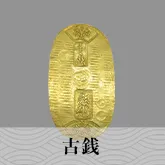



 査定・出張費無料
査定・出張費無料 キャンセル無料
キャンセル無料 安心・信頼
安心・信頼 丁寧・迅速
丁寧・迅速