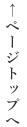コラム
-
日本刀・刀の鑑定機関とは?鑑定区分や鑑定のポイントを解説
公開日 2025/04/18
更新日 2025/04/30
-

日本刀や刀剣類はコレクターアイテムとしても人気が高く、日本の歴史や文化を感じられる品物のひとつとされています。
古代には武器として携帯されていましたが、刀匠の個性や流派による違い、装身具としての重要性が高まるにつれて、さまざまなデザインの刀が作られてきました。
刀の時期や希少性などによって価値が変わるため、高い価値が期待される刀剣は、専門機関に鑑定を依頼し、鑑定書を取得しておくことが重要です。
この記事では、日本刀や刀剣の主な鑑定機関について紹介します。刀の鑑定区分や鑑定の格付けについて、鑑定審査を受ける際のポイントも解説しています。
日本刀の高価買取なら美観堂にお任せください!
買取方法・買取相場・相見積もりの依頼はこちらのバナーをクリック目次
日本刀や刀剣の主な鑑定機関

日本刀や刀剣の鑑定機関は、国による機関、日本美術刀剣保存協会、その他の民間団体に分類されます。歴史的価値が高い刀が発見されたときは、文化財保護法に基づき日本国が鑑定を行うことがあります。
ここからは、鑑定機関ごとの特徴をみていきましょう。
日本国
非常に重要な歴史的・美術的価値を持つ刀剣は、国によって鑑定・評価が行われます。
1950年(昭和25年)に制定された文化財保護法に基づき、国宝や重要文化財の指定を行うことを目的として、各都道府県に設置されている文化財保護委員会が鑑定を行ってきました。
刀剣の中には、希少性の高いものや歴史的価値の高いものがあります。文化財保護委員会から鑑定を受けた刀剣には「指定書」と呼ばれる鑑定書が付けられ、国宝・重要文化財・重要美術品のいずれかに分類されます。
日本美術刀剣保存協会
公益財団法人 日本美術刀剣保存協会(日刀保)は、1948年(昭和23年)に設立された機関です。国内で唯一文部大臣の認可を受けており、信頼性の高い専門機関として知られています。
刀剣類、刀装、刀装具の鑑定や審査に加え、分類の指定や台帳の作成も行っています。台帳の作成は、歴史的または美術的価値のある刀剣の所在を明確にする業務です。
その他の業務として刀剣博物館を運営し展示活動を行い、刀剣類の整備や相談にも応じています。
その他の団体
特別非営利活動法人 日本刀剣保存会など、独自に鑑定を実施している団体もあります。
また、美術品や骨董品を扱う店舗や組織にも鑑定の専門家が常駐し、専門的な立場から鑑定を行うことがあるため、専門家による見極めが必要な場合は、相談を検討してみましょう。
刀の鑑定区分

刀の鑑定区分は、日本国の宝とされる『国宝』をはじめ、いくつかの種類に分類されています。
ここからは、日本国と日本美術刀剣保存協会がそれぞれ定めている鑑定区分について確認していきましょう。
日本国における鑑定区分
日本では、「国宝」「重要文化財」「重要美術品」の3段階に分けて鑑定区分を設けています。
国宝
国宝は日本国の宝とされる品物などを指し、文化的または歴史的観点で特に価値が高いと評価されるものです。
大きなくくりでは重要文化財に含まれますが、その中でも世界文化の観点から特に高い価値を持つものが国宝に指定され、「たぐいない国民の宝たるもの」と位置づけられています。
国宝に指定されている刀剣は100点以上あり、全体のおよそ7割が太刀(たち)とされています。さらに、鎌倉時代に作られたと考えられるものが全体の約8割を占めています。
重要文化財
重要文化財は、文化庁が管轄する文化財保護法で「有形文化財」として工芸品に分類されるもので、さらに芸術・歴史・学術的な観点で重要とされるものです。
刀剣類はいずれも形のある(有形)文化財ですが、そのうち芸術的または学術的に重要なものだけが選定され、重要文化財に指定されています。
重要美術品
重要美術品は、文化財保護法が施行される以前の法律「重要美術品等の保存に関する法律」に基づいて認定されている有形文化財です。
文化財保護法が施行されてからはすべてが有形文化財に指定されていますが、現在も一部の刀剣は、重要文化財に次ぐ価値を持つものとして「重要美術品」の呼称が使われています。
日本美術刀剣保存協会における鑑定区分
日本美術刀剣保存協会が定めている刀剣の分類は「特別重要刀剣」「重要刀剣」「特別保存刀剣」「保存刀剣」の4段階です。
ここからは、日刀保によって定められた鑑定区分を詳しくみていきましょう。
特別重要刀剣
特別重要刀剣は、重要刀剣の中でも保存状態が極めて良く、出来映えが優れているものを指します。
特別重要刀剣とは、重要刀剣の中でも特に出来栄えがよく、保存状態に優れたものを指します。特別重要刀剣は、国指定の重要美術品のうち上位のものと同等の価値があると判断されます。
重要刀剣
重要刀剣は、平安時代から江戸時代までの作品で、特に保存状態や由緒が良く、重要美術品に準じた品質を持つ刀剣です。
特別重要刀剣ほどの出来栄えではありませんが、全体的に出来が良く保存状態も良いものを指します。国指定の「重要美術品」と同等の価値があると判断されます。
室町時代〜江戸時代に作刀された刀剣では、生ぶ茎(うぶなかご※)で、銘が刻まれているものに限られます。南北朝時代までの刀剣は無銘のものでも重要刀剣として選定されます。
※作刀当時のままで、磨き上げを施していない茎のこと
保存刀剣
保存刀剣は、江戸時代までに作刀され、正しい銘がある刀剣、または南北朝時代以前に作られた著名な銘を持つ刀剣とされています。
銘が存在しない場合でも、作刀の年代や生産地などが明らかであり、鑑賞に耐えうる出来栄えであれば、保存刀剣に該当します。
特別保存刀剣
特別保存刀剣は、保存刀剣の中でも特に保存状態と出来栄えが良く、美しさを損ねていないものが該当する鑑定区分です。
国指定の「重要美術品」のうち、上位の刀剣と同等のものに相当すると考えられています。
特別貴重刀剣・貴重刀剣
特別貴重刀剣および貴重刀剣は、公益財団法人 日本美術刀剣保存協会が1948年(昭和23年)に設けた認定制度に基づく区分です。のちにこの制度は廃止されたため、現在では使用されていません。
認定書にこの鑑定区分が記載されている場合、それは現在では効力を失っている状態です。そのため、公益財団法人 日本美術刀剣保存協会による鑑定を受け直すことが推奨されています。
刀剣の鑑定の格付け

刀剣の鑑定における格付けは、「業物(わざもの)」という言葉で表現されています。
日本が統一された江戸時代に入り、1596~1780年に作刀された新刀について、切れ味を確かめるための試し切りを実施する際に「最上大業物」「大業物」「良業物」「業物」の位が設定されました。
業物の下位には、標準的な切れ味を持つ「準業物」や、切れ味に欠ける「なまくら」なども含まれます。
ここからは、「最上大業物」「大業物」「良業物」「業物」のそれぞれについてみていきましょう。
最上大業物
最上大業物は、刀剣としての出来栄えと切れ味の両方が最上級とされる刀剣に対する評価です。
優れた技術を持つ刀匠であっても、このレベルの刀剣を作刀できるとは限らない、希少価値の高いものを指します。具体的な刀としては、「長曽祢虎徹(ながそねこてつ)」「孫六兼元(まごろくかねもと)」などを指します。
大業物
大業物は、最上大業物の次に高いランクであり、優れた切れ味を持つ刀剣に対する評価とされています。
最上大業物に次いで手に入れることが難しいものであり、「長船祐定(おさふねすけさだ)」や「和泉守国貞(いずみのかみくにさだ)」が指定されています。
良業物
良業物は、大業物に次ぐ切れ味を持っていると評価される刀剣です。
「粟田口忠綱(あわたぐちただつな)」や初代・2代の「越前康継(えちぜんやすつぐ)」を含む刀剣が指定されています。
業物
一般的に切れ味が良く、良業物に次ぐレベルの刀剣です。
武士が身につける刀のランクはこの業物が基本とされ、「法城寺正弘(ほうじょうじまさひろ)」や初代〜3代の「河内守国助(かわちのかみくにすけ)」などが指定されています。
刀の鑑定審査を受ける際のポイント

所有している刀の鑑定審査を受けるときは、在銘または無銘であるか、刀装や茎の状態を確認します。
詳しい鑑定は専門的な知識をもつ鑑定士が行いますが、ここでは審査のポイントを詳しくみていきましょう。
在銘か無銘かどうか
「銘(めい)」とは、刀のグリップ部分である茎(なかご)にある作者のサインです。
銘の歴史は古く、700年頃からすでに刀工の名前を刀に施すようになったといわれています。磨き上げによって削られてしまうため刃には施さず、茎の部分に施すようになったと考えられています。
銘を確認することで制作者や制作された年代、刀の価値などが予測できるため、年代物の刀にとっては非常に重要な要素といえるでしょう。
鑑定士は刀工名・流派といった部分を見極めながら、刀全体の真贋も確認します。無銘(銘が切られていない)ものは、銘が何であるかを突き止める作業を行います。
刀装のチェックとランク
刀装とは、刀剣を装う(飾る)ために使われる物品です。具体的には、鞘(さや)・鍔(つば)・柄(つか)・下緒(さげお)・鎺(はばき)・目貫(めぬき)などです。
かつては刀剣本体を守るために補強するアイテムとして作られていましたが、武器である以外にも刀が身分や権力を示すためのアイテムとみなされるようになったことから、刀装具にも華やかさが付与されました。
刀を鑑定する場合、本体だけではなくこの刀装も真贋や美しさを見極める必要があります。一式が揃っているか、作られた当時のままの色や形を維持しているかといった保存状態をチェックします。
刀装にも保存刀装や特別保存刀装といったいくつかのランクがあるため、どのランクに該当するかを判断します。
茎のチェックと流派
茎(なかご)は、日本刀のうち刃がついていない部分の名称です。
刃のついている上身(かみ)と茎をどちらも確認し、茎については錆びの程度や色合いなどを確認します。
上身を先に作り、全体のバランスを見ながら茎を作っていくため、刀匠の個性や作刀された時代、流派が表れやすい部分ともいわれています。
保存刀剣から受ける
鑑定審査では、保存刀剣に該当するかどうかが重要な判断基準となります。保存刀剣に該当すると判断された場合は、特別保存刀剣や重要刀剣といった上位区分に進む可能性があります。
保存刀剣と特別保存刀剣の審査は同時に受けられますが、重要刀剣に該当するには、まず特別保存刀剣の審査に合格する必要があります。
同様に、重要刀剣の上位である特別重要刀剣に該当するには、重要刀剣の審査に合格していることが前提となります。
関連記事:日本刀の名刀一覧に名を連ねる天下五剣・天下三作の特徴について
刀の鑑定は専門的な知識をもつ鑑定士へ依頼
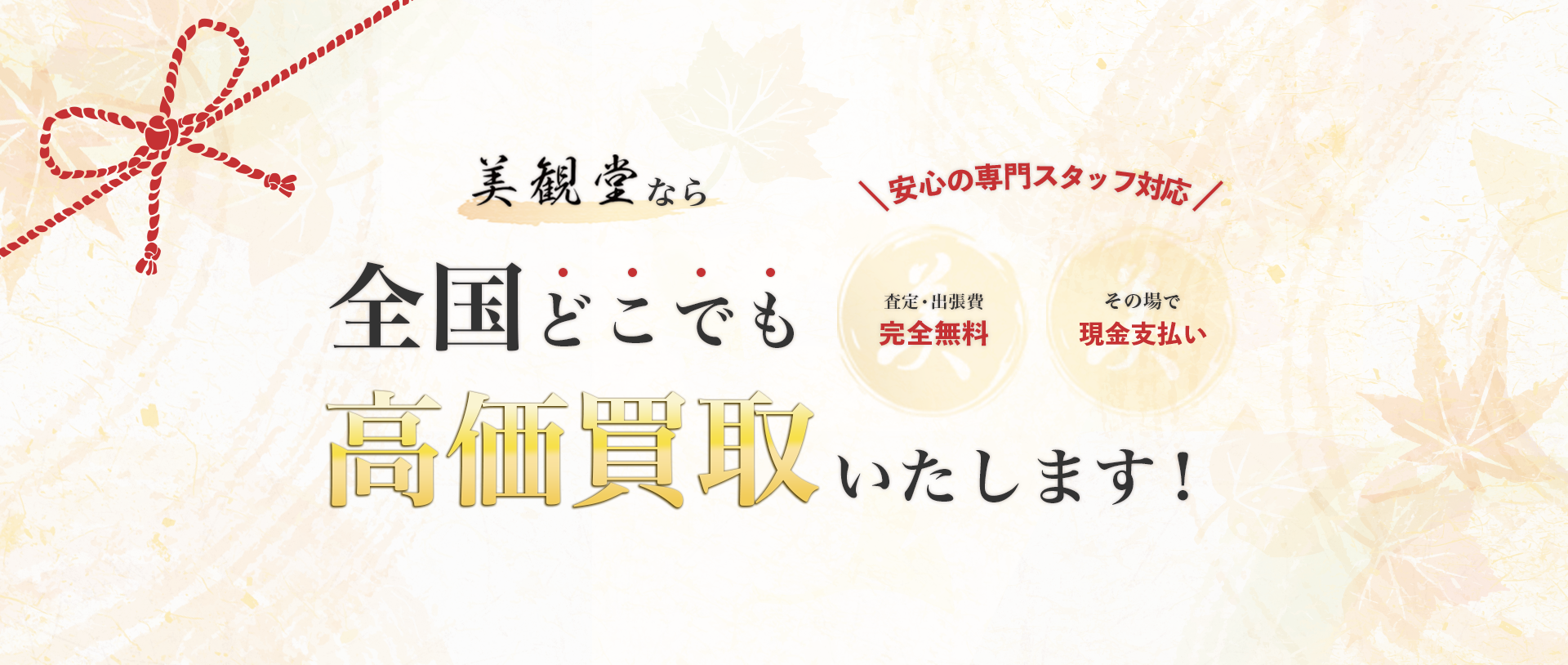
今回は、本刀の鑑定機関とその鑑定区分、鑑定の際のポイントについて解説しました。
刀剣にはさまざまな種類があり、作刀された時代・刀匠・流派・保存状態が異なります。正しく作刀され、大切に保存されてきたものほど高い価値を持ちます。一方で、流派に関係なく古い時代の刀には歴史的価値が認められる場合もあります。
日本刀などの刀剣を売却する際は、専門的な知識を持つ鑑定士に依頼することが重要です。日本刀・刀剣の買取なら美観堂にお任せください。15年以上の鑑定歴をもつ鑑定士が在籍しています。
この記事の監修者

義村 安悟(よしむら あんご)
《経歴》
美観堂 大阪本店店長 査定歴15年
《コメント》
複数の店舗で店長としての経験を活かし、身の回りのさまざまなジャンルのお品物を丁寧に査定しています。特に古美術品の買取においては、作品の歴史や芸術的価値、作家や時代の背景を考慮して査定を行っており、状態だけでなく市場の動向を踏まえ、公正で適正な価格設定を心がけております。
また、遠方にお住まいのお客様からのご依頼も多い中、出張買取を通じて、さらにお役に立てるよう努めてまいりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。《許可証》
古物商営業許可番号:第62111R051143号
美観堂買取
〒542-0062大阪府大阪市中央区
上本町西5丁目3-3ワンダー5ビル1F
選ばれる理由
|
|
|
|


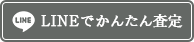
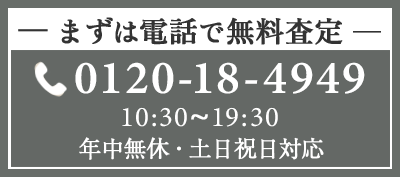





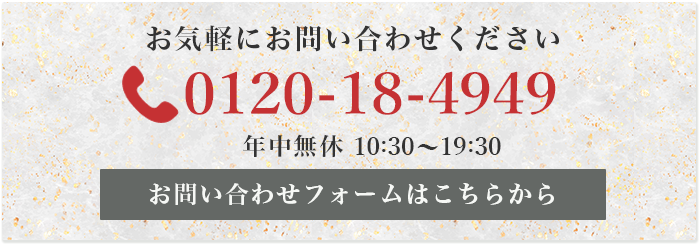



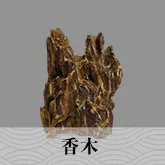
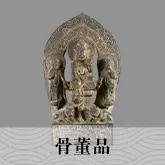


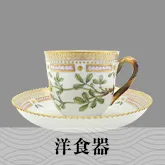
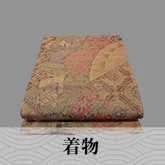
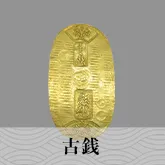



 査定・出張費無料
査定・出張費無料 キャンセル無料
キャンセル無料 安心・信頼
安心・信頼 丁寧・迅速
丁寧・迅速