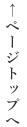コラム
-
日本刀の名刀一覧に名を連ねる天下五剣・天下三作の特徴について
公開日 2025/04/18
更新日 2025/04/30
-

日本刀の価値が気になる方、売却を検討している方に向けて、日本刀の名刀一覧について解説します。
「所有している日本刀を売却したい」と思ったときに、やはり気になるのは「価値」ではないでしょうか?名刀一覧に名を連ねるような日本刀であれば、歴史的価値が高く、数百万円で買い取られることもあります。
そこで今回の記事では、名刀とされる日本刀の一覧をご紹介します。参考にしていただければ、歴史的価値が高く、高額査定が見込まれる日本刀について、理解を深めていただけることでしょう。
日本刀の高価買取なら美観堂にお任せください!
買取方法・買取相場・相見積もりの依頼はこちらのバナーをクリック目次
日本刀の名刀とは?

「名刀」と呼ばれるのは、一般的に次のような条件を満たした作品であるとされます。
【名刀の条件】
- 優れた作刀者によって作られたこと
- 知名度の高い刀であること
- 切れ味や美しさに優れていること
優れた美しさを持つ刀には「号」がつけられていました[1]。号とは刀の愛称にあたるものであり、姿の美しさや逸話を元に授けられたものです。安土桃山時代には「光徳刀絵図」が描かれており、筆裁きによって、刀の沸や匂いに至るまで、「刀の美しさ」として丁寧に描き分けられていました。
以上のように古来、美しい刀は名刀とされてきましたが、現代では知名度の高さなども評価の基準とされています。
日本刀の名刀で有名な天下五剣とは?

名刀として知られる「天下五剣」とは、次に挙げる「五腰の名刀」のことを指します。数ある刀の中でも歴史に名を残す名刀とされており、国宝や重要文化財に指定されるほどの価値があると評価されています。
【天下五剣】
- 童子切安綱(どうじきりやすつな)
- 三日月宗近(みかづきむねちか)
- 鬼丸国綱(おにまるくにつな)
- 大典太光世(おおてんたみつよ)
- 数珠丸恒次(じゅずまるつねつぐ)
これらの刀がなぜ「五腰」と呼ばれるようになったのかは明らかではありません。しかし江戸時代後期の書物には上記五腰が揃って登場しており、現代においても代表的な名刀とされています。
関連記事:日本刀の銘の種類・13パターンの意味と無銘の刀がある理由について
日本刀の名刀である天下五剣一覧

ここでは、名刀とされる五腰の日本刀について、その特徴を紹介します。
名称 種類 刃長 鑑定区分 伝来 所蔵 童子切安綱 太刀 80.0cm[2] 国宝[2] 酒呑童子を切った太刀であるとされる 東京国立博物館 三日月宗近 太刀 80.0cm[3] 国宝[3] 五腰の中でも特に優美で、見る者を圧倒する美しさを備えている 東京国立博物館 鬼丸国綱 太刀 78.2cm 御物 北条時頼の夢に出てきていた鬼を切ったとされる 皇室 大典太光世 太刀 66.0cm 国宝 病に苦しむ豪姫を救ったとされる 前田育徳会 数珠丸恒次 太刀 82.1cm 重要文化財 仏法との関連が深い逸話はない 兵庫県・本興寺 それぞれの日本刀について、名刀一覧として解説します。
1:童子切安綱
国宝に指定されている「童子切安綱」は、豊臣秀吉、徳川家康、徳川秀忠が所有していたとされます[2]。小乱れの変化が多様な刃文と、腰反りの高さが特徴とされています[2]。
名作とされる五腰の1振であり、国宝に指定されたのち、現在は東京国立博物館に所蔵されています。10~12世紀ごろの平安時代に制作されたと伝えられる刀です[2]。
童子切安綱に関する逸話
「童子切安綱」は、酒呑童子と呼ばれる鬼を討ち取ったという逸話に由来して名付けられたとされています。酒呑童子とは室町時代に生まれたとされる伝説上の鬼です[2]。しかし逸話では、平安時代に暴虐を尽くした酒呑童子退治を依頼された源頼光が、童子切安綱を用いて討ち取ったとされます[2]。
童子切安綱を作った刀工
平安時代の刀鍛冶である「伯耆安綱(ほうきやすつな)」によって作られたと伝えられています。鳥取県西部で暮らしていた刀鍛冶で、優れた刀を多く残しました[2]。
2:三日月宗近
名作とされる五腰として次にご紹介するのは、「三日月宗近」です。室町時代には名作とされる五腰のひとつとされていたと伝えられており、茎から腰にかけての反りの強さが特徴的[3]。また刃文に三日月の形状が見られることから、三日月宗近との名前が付けられたとされています[3]。豊臣秀吉の正室・高台院が所持していたと伝えられ、没後には徳川秀忠へ贈られた逸品とされています[3]。
三日月宗近に関する逸話
伝説的な逸話は残っていませんが、非常に優美で迫力に満ちた刀として、高く評価されています。制作されたのが1,000年以上前であるにも関わらず汚れやシミがなく、神秘的で上品な印象を備え、圧倒的な美しさを誇る作品です。元内閣総理大臣であった犬養毅が鑑賞した際には、その迫力に圧倒され、思わず頭を垂れたと語った逸話が伝えられています。
三日月宗近を作った刀工
三日月宗近を制作した刀工は、名刀工とされる「宗近」であり、京都の三条に住んでいたとされています。そのため三条宗近と呼ばれることが多く、作品の銘には「宗近」または「三条」のいずれかが刻まれている例が確認されています。
3:鬼丸国綱
北条時頼の命によって制作されたのが「鬼丸国綱」です。鎌倉時代に制作された作品と伝えられています。この後に紹介する逸話にもあるように、鬼丸国綱は子鬼を討伐したとされる刀です。その後、「鬼丸」という号が与えられ、北条家の宝刀として重宝されたと伝えられています。現在では重要文化財として指定されており、皇室にて所蔵されています。このため、名作とされる五腰の中で「御物」として扱われている唯一の刀とされています。
鬼丸国綱に関する逸話
鬼丸国綱は、北条時頼を苦しめた子鬼を討伐したとされる刀として知られています。討伐されたのは現実に実在していた鬼ではなく、北条時頼の夢の中に毎晩現れた鬼です。鬼を退治しようとお祓いを受けましたが、その後も夢に現れる鬼に苦しめられ続けたと伝えられています。
しかしある日、夢の中に刀が現れ、錆びを落としてくれたら子鬼を退治すると北条時頼に伝えます。早速北条時頼が刀を清めて寝室に立てかけてから眠ると、刀が倒れて火鉢を切断。その切断された飾りは、夢の中に出てきた子鬼と瓜二つだったと言われます。
上記のような逸話から「鬼丸国綱」と呼ばれるようになり、北条時頼はその後、夢の中の鬼に苦しませられることはなくなりました。
鬼丸国綱を作った刀工
作刀した刀工は、現在の京都府南部に住んでいた「国綱」です。鎌倉時代の刀鍛冶として活躍した刀工であるとされますが、どのようにして鬼丸国綱を制作したかの詳細は明確になっていません。鬼丸国綱およびその子や養子が手がけた刀は、実戦での使用に適しており、頑強さが特徴だったとされています。
4:大典太光世
大典太光世は名作とされる五腰の中でも、霊力を持つ刀として知られています。足利家から徳川家へと渡り、前田家へと渡ってからは前田家の宝刀として、現在も前田家において大切に受け継がれていると伝えられています。「重宝三振」「名物」「国宝」「天下五剣」と、4つの肩書を持つ唯一の刀でもあります。江戸時代の名刀リストである「享保名物帳」にも、名物として記載されました。
大典太光世に関する逸話
もともと霊力を持つとされていた大典太光世には、霊力の存在を示す逸話も伝えられています。それは豪姫の病魔を退治したとする話です。前田利家の四女であった豪姫は病に苦しんでいた豪姫の枕元に刀を置いたところ、すぐに体調が回復したと伝えられています。そして本来の持ち主である豊臣秀吉に刀を返却したところ、豪姫の病状は悪化。また刀を借りて枕元に置いたところ、再び病状は快方に向かったと伝えられています。返却と借用を三度繰り返した後、豊臣秀吉が返却の必要はないと述べたことで、最終的に前田家の所有となりました。
大典太光世を作った刀工
作刀したのは、「三池典太光世」です。平安時代の刀工であり、現在の福岡県南部に居住し、三池派という刀工集団を創設した人物とされています。刀に魂を宿すとされる高度な技術を有していたと伝えられています。
5:数珠丸恒次
「数珠丸恒次」は、日蓮宗の開祖である日蓮聖人が愛用していたことで知られています。兵庫県尼崎市の本興寺が所蔵していることからもわかるように、仏法と深く関係する刀とされ、切れ味や美しさよりも仏教上の護身具としての意味合いが強いと伝えられています。
1920年に兵庫県尼崎市在住であった刀剣鑑定士によって発見され、日蓮宗の本興寺に奉納されたと伝えられています。そして現代まで大切に保管されてきた数珠丸恒次は、毎年11月3日に開催される「虫干会 大宝物展」にて公開されています。
数珠丸恒次に関する逸話
日蓮聖人は、村民の強い要望を受けて守り刀として数珠丸恒次を所有していたと伝えられています。もともとは仏に遣える身であるからと、武器を持つことを拒んだ日蓮聖人でしたが、その身を案じた村民からの強い要望によって受け取ったのが数珠丸恒次でした。その後も柄に数珠をかけ、破邪顕正を祈念する太刀として携えていたとされています。
数珠丸恒次を作った刀工
平安時代から鎌倉時代にかけて活躍した「恒次」が作刀しました。現在の岡山県倉敷市で活動していた刀鍛冶であり、青江派に属していました。青江派は刀剣愛好家の間でも広く知られ、高度な作刀技術を持つ刀工集団とされています。青江派を継いだ三兄弟の次男であり、功績を称える官名である「受領命」を朝廷から授かったこともあるほどの実力者でした。
天下五剣が日本刀の名刀と言われる理由

天下五剣が日本刀の名刀とされる理由は、今なお明確にはなっていません。最初に解説したように、江戸時代後期の書物には上記五腰が揃って登場しました。「天下出群之名刀」や「天下出群之名劒にて右五振ノ内」として記載されており、名作とされる五腰に相当することを示唆しています。しかし「天下五剣」という表現が記された書物は、現在のところ確認されていません。
一説では室町時代から安土桃山時代には選出されていたとされています。しかし明治時代以降に五腰の名が広まったとの説もあり、確かなことは明らかになっていないのが現状です。
関連記事:日本刀の値段を決める基準とは?基本ポイント&3つの基準について
日本刀の名作を手がけた天下三作とは?

日本刀の名刀一覧に挙げられるのは、「天下五剣」だけではありません。「天下三作」も日本刀名刀一覧のひとつとして広く名を知られています。
天下三作とは、三人の名工が鍛えた刀を指すとされています。豊臣秀吉によって選定されたと伝えられています。現代にまで受け継がれてきた天下三作について、その特徴を三人の名工の作風から読み解いていきます。
天下三作1:粟田口吉光
まず「粟田口吉光(あわたぐちよしみつ)」は、京都の粟田口で活動していた刀鍛冶で[4]、短刀を得意としていました。通称は「藤四郎」であり、制作した短刀も「藤四郎」と呼ばれることがあります。江戸時代には、武将や大名にとって欠かせない存在とされるまでの地位を築いたとされています。
内反りの作品が多いこと、重ねが厚いこと、小互の目の刃文を持つことが特徴とされています。特に「一期一振藤四郎」は、太刀でありながら粟田口吉光の最高傑作として高く評価されています。
天下三作2:五郎入道正宗
「五郎入道正宗(ごろうにゅうどうまさむね)」は鎌倉時代から南北朝時代にかけての刀工です。現在の神奈川県にて活動していました[4]。知名度の高い刀を多く制作した刀工として知られており、「享保名物帳」には42振も掲載されています。
反りが浅い作風が特徴であり、刃文や地景の美しさと華やかさが際立っている点も、作風の特徴とされています。
銘を切ることが稀であったため、現代に残る作品のほとんどが無銘[4]ですが、作品のひとつである「伝正宗」は無銘ながら特別重要刀剣として認められています。
天下三作3:郷義弘
南北朝時代に、現在の富山県で活動していた[4]のが「郷義弘」だと伝えられています。名工でありながら早くに亡くなったため作品数は少なく、さらに銘を切らなかったため現存する作例が極めて少ないことから、希少な刀工と評価されています。
反りが深く、刃文が大きく乱れる点が作風の特徴ですが、鎌倉時代の様式を継承した優美な刀を制作した例もあります。代表作として「稲葉江」「富田江」があります。
名刀一覧に名を連ねる日本刀は歴史的に重要な価値を持つ
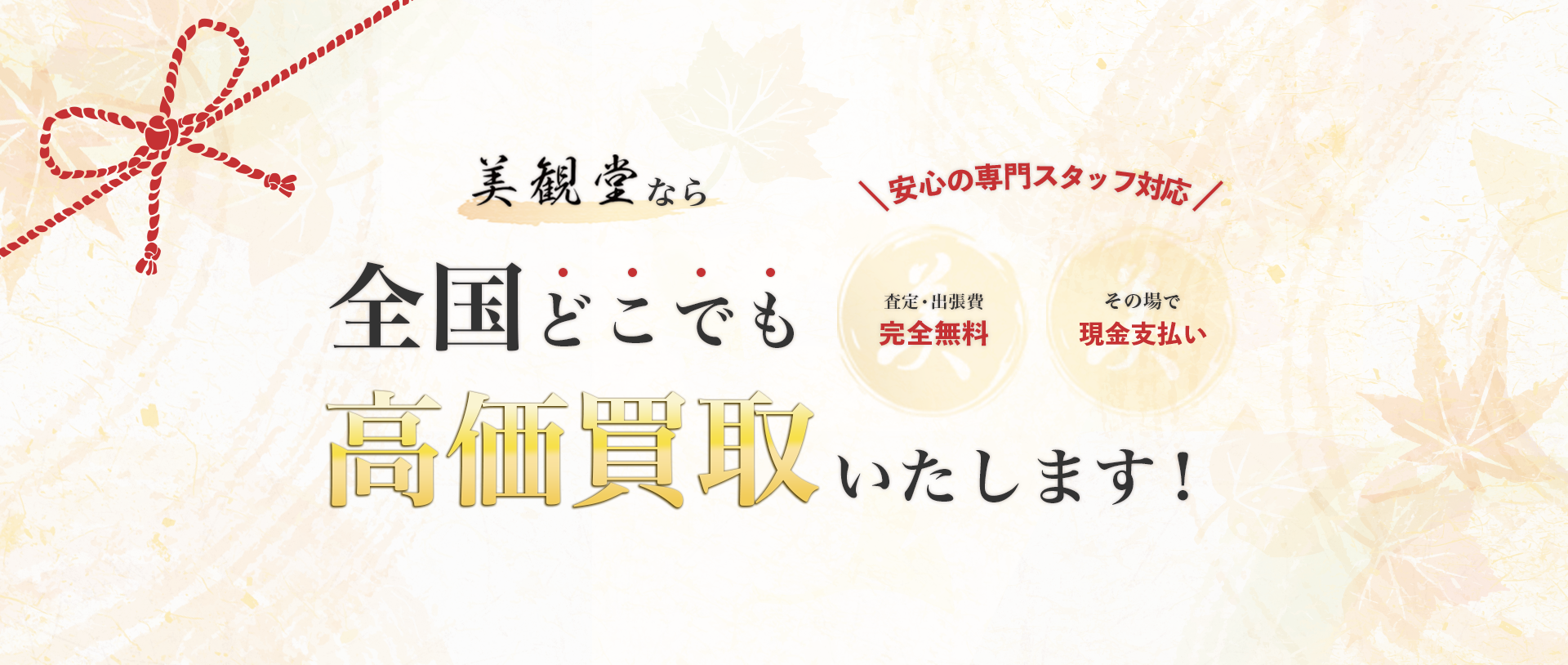
いかがでしたでしょうか?ここまでの内容を通して、日本刀名刀への理解が深まったのではないでしょうか。名刀とされる作品は美しさや切れ味に優れているだけでなく、歴史的にも高い価値を有すると評価されています。
美観堂では日本刀専門の鑑定士が丁寧に査定を行い、名刀一覧に名を連ねる日本刀でもその価値に見合った査定額をご提示いたします。
その際は、日本刀・刀剣の買取なら美観堂の無料査定をご利用ください。[1]
参照:JSTAGE:(PDF)日本刀の伝統的作刀技術と美術的価値
[2]
参照:e国宝:太刀 銘安綱(名物童子切安綱)たち めいやすつな めいぶつどうじぎりやすつな
[3]
参照:e国宝:太刀 銘三条(名物三日月宗近)たち めいさんじょう めいぶつみかづきむねちか
[4]
この記事の監修者

義村 安悟(よしむら あんご)
《経歴》
美観堂 大阪本店店長 査定歴15年
《コメント》
複数の店舗で店長としての経験を活かし、身の回りのさまざまなジャンルのお品物を丁寧に査定しています。特に古美術品の買取においては、作品の歴史や芸術的価値、作家や時代の背景を考慮して査定を行っており、状態だけでなく市場の動向を踏まえ、公正で適正な価格設定を心がけております。
また、遠方にお住まいのお客様からのご依頼も多い中、出張買取を通じて、さらにお役に立てるよう努めてまいりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。《許可証》
古物商営業許可番号:第62111R051143号
美観堂買取
〒542-0062大阪府大阪市中央区
上本町西5丁目3-3ワンダー5ビル1F
選ばれる理由
|
|
|
|


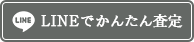
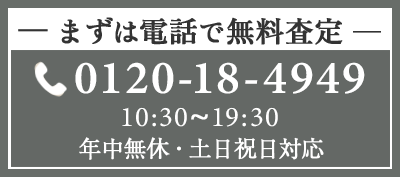





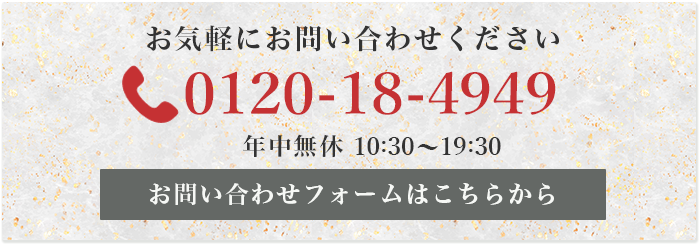



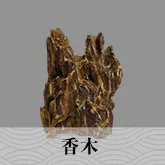
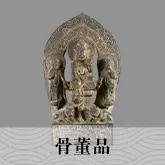


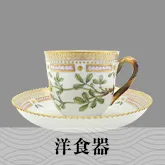
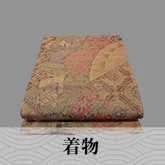
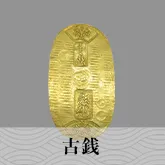



 査定・出張費無料
査定・出張費無料 キャンセル無料
キャンセル無料 安心・信頼
安心・信頼 丁寧・迅速
丁寧・迅速